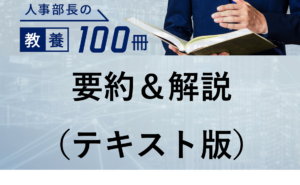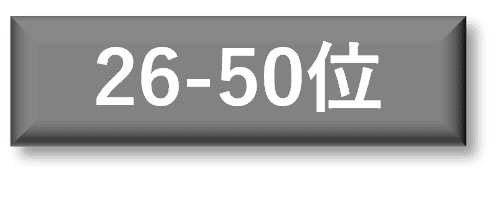


- 第26位「福翁自伝」福沢諭吉
- 第27位「モモ」エンデ
- 第28位「善の研究」西田幾多郎
- 第29位「歴史とは何か」カー
- 第30位「般若心経」玄奘三蔵訳
- 第31位「エミール」ルソー
- 第32位「こころ」夏目漱石
- 第33位「ハムレット」シェイクスピア
- 第34位「チーズはどこへ消えた?」S・ジョンソン
- 第35位「方法序説」デカルト
- 第36位「代表的日本人」内村鑑三
- 第37位「オイディプス王」ソポクレス
- 第38位「人生論」トルストイ
- 第39位「生きがいについて」神谷美恵子
- 第40位「超入門 失敗の本質」鈴木博毅
- 第41位「ソクラテスの弁明」プラトン
- 第42位「茶の本」岡倉天心
- 第43位「ブッダのことば(スッタニパータ)」釈迦
- 第44位「フランクリン自伝」フランクリン
- 第45位「昭和16年夏の敗戦」猪瀬直樹
- 第46位「マネジメント」ドラッカー
- 第47位「文明論之概略」福沢諭吉
- 第48位「ニコマコス倫理学」アリストテレス
- 第49位「自助論」スマイルズ
- 第50位「幸福論」ラッセル
第26位「福翁自伝」福沢諭吉
【どんな本?】
明治の大思想家、福沢諭吉の自伝。福澤の口述を新聞記者が文字に起こして連載した、明治版「私の履歴書」全15編。
西洋の「フランクリン自伝」と並ぶ自伝文学の名著中の名著。長崎からの脱出、学問への没頭、渡米、暗殺未遂など、一瞬たりとも読者を飽きさせない福澤の筆力に脱帽させられる一冊。慶應受験者はもちろん、教養を志す全ての人にとって「学問のすすめ」「文明論之概略」「福翁自伝」の3冊は特に必読。
【福澤諭吉が伝えたいこと】
私は昔から身分制度や因習を非合理だと思っていた。自分は下級武士だったので、金も権力も全くなかったが、学問一つで世の中に貢献できるまでになった。幕府の門閥制度鎖国主義は嫌いだが、勤王家は幕府以上の鎖国攘夷だから、じっと中立独立を決め込んでいたのだ。
好き!→お酒、タバコ、運動、独立、勉強
嫌い!→攘夷、封建制度、儒教、借金、役人、血
第27位「モモ」エンデ
【どんな本?】
ドイツ人作家ミヒャエル・エンデによる長編童話。1974年にドイツ児童文学賞を受賞。現代社会の枠組みから外れた不思議な少女「モモ」が、時間泥棒に奪われた現代人の時間を取り戻す冒険ファンタジー。
人間本来の生き方を忘れてしまっている現代人への警鐘という要素はもちろんのこと、モモと灰色の男たちとの手に汗握る攻防は、大人が読んでも十分に楽しめる。児童文学の中でも深い学びが得られる名作中の名作。
【エンデが伝えたいこと】
現代人は常に時間に追われて忙しくしている。「将来のため」「よい暮らしのため」と言うが、これでは生きることの意味や喜びを見失っている。「時間泥棒」を生み出したのは、効率ばかりを追う現代人自身なのである。
第28位「善の研究」西田幾多郎
【どんな本?】
「哲学」という概念がなかった明治日本において、論理重視の西洋思想と自身の禅体験を融合し、主観・客観が分離する以前の原初的な「純粋経験」を実在とするという独自の立場を創造した、日本最初の哲学書。
カントの純粋理性批判と並び、とにかく「難しい」と言われるいわくつきの骨太本。しかし、西洋思想と東洋思想の融合に挑戦した日本初のオリジナル哲学は、思考や教養の幅を広げること間違いなし。本サイトでは、詳細な注釈と解説がついた講談社学術文庫版(小坂国継注釈)をオススメする。
※第3編「善」・第4編「宗教」が西田の言いたいこと、第1編「純粋経験」・第2編「実在」が西田哲学の理論的基礎となっているので、第3編から読むと読みやすい(西田自身も第1編は省略してよいと言っている)
【西田幾多郎が伝えたいこと】
善とは一言でいえば「人格の実現」である。人間の本性及び宇宙の統一原理は同一であって、そこには後天的な知識や判断の影響を受けない普遍的な「意志」が存在する。その意志を実現することが人格の実現であり善の実践である。
「この世界がどうあるか」「人間はどう生きるべきか」という実在を知るには「純粋経験(≒直感)」が必要であるという点は西洋哲学的(イギリス経験論)であるし、その究極が「知的直観(≒自分と宇宙が一致する梵我一如)」であるという点は東洋哲学的(ウパニシャッド哲学)である。
第29位「歴史とは何か」カー
【どんな本?】
歴史哲学の大家E・H・カーが1961年にケンブリッジ大学で講演した「歴史とは何か」を書籍化したもの。
歴史とは客観的事実を集めることではなく、事実の背後にある価値体系や思想体系まで含めて解釈し、後世に伝達することだと主張する。欧米では、歴史を学ぶ者にとって「必読書」と言われている。
【カーが伝えたいこと】
過去の諸事件に秩序を与え、これを解釈し、社会の役に立てることが歴史家の仕事である。しかし、いくつか心に留めておくべきことがある。
まず、歴史は科学ではない。次に完全に客観的な歴史などあり得ない。偉人の成果だけに着目して歴史を把握することも誤っている。また、歴史にゴールは無いし、歴史には進歩も後退もある。ただ、進歩を信じ、後世のためにそれまでの経験を伝達する義務を果たすだけである。
第30位「般若心経」玄奘三蔵訳
【どんなお経?】
大乗仏教の経典『大般若経』600巻のエッセンスを262文字に凝縮。釈迦が到達したとされる真理を含めて、それまでの仏教で信じられてきた教義を否定しまくるロックなお経。その破壊力は「東洋のニーチェ」といった趣。
何しろこれ一冊で仏教の神髄が理解できるのだから、読まない手はない。神を信仰して天国に行こうとするユダヤ教やキリスト教とは正反対に、「世の全ては空(くう)である」ことを体得することで人生の苦しみから逃れるという斬新なアプローチが展開される。Apple創業者のスティーブ・ジョブズが般若心経に影響を受けていたことは有名。
【般若心経が伝えたいこと】
「完全なる智慧」から見れば、世の中のあらゆる現象や物質は実体を持たず、 無限の関係性の中で絶えず変化するものであって、人間が持つ苦悩や災いなど、そもそも無い。だからあなたは苦しむ必要などないのだ。
第31位「エミール」ルソー
【どんな本?】
ルソー思想の集大成であり、教育学の古典中の古典。少年エミールがソフィーと結婚するまでの25年を「私」が見守り、助言し、文明社会によってゆがめられない自然人の理想を目指して指導するという哲学・道徳・教育小説。
『社会契約論』が民主主義の制度論である一方、本書は民主主義を担う人材論と言える。
「近代教育学のバイブル」として、教育に携わる人にとっては必読。加えて、お子さんを持つ全ての方にもおすすめ出来る教育論の定番。ルソー自身は「私の最も価値のある最良の書」「20年の省察と3年の執筆の成果」と評価。ドイツの大哲学者カントが、時間を忘れるほど熱中して読んだことでも知られる。
【ルソーが伝えたいこと】
子供とは「未熟な大人」ではなく、「子供」という自然の存在である。また、せっかく子供は「善い」存在で生まれてくるのに、社会が人間を堕落させる。よって、大人は子供を文明社会の悪影響から守りつつ、自然の発育段階に応じて教育するべきである。
誕生から15歳くらいまでは、理性も道徳も理解できないのであるから、まずは自分自身のために生きる「自然人」として教育すべきである。一方、分別の付く年齢に達したら、他者に対する思いやりや共感能力を育てる「社会人」として育てればよい。
また、子供には以下3種類の先生によって教育されるべきである。 ①自然(人間の先天的な能力や知性を引き出す教育) ②人間(親や教師による教育) ③事物(経験から学ぶ教育)
このようにして教育を受けた子供が、自由・平等を基本理念とする民主主義社会を担う人材となっていくのだ。
第32位「こころ」夏目漱石
【どんな本?】
明治の文豪 夏目漱石後期の作品。私が慕う「先生」が、一人の女性を巡って親友Kを裏切った過去を悔んで、自らも命を絶つ物語。人の孤独や生きにくさを描き出す。
日本における小説分野の最高峰。日本の文庫本の発行部数では歴代第1位。新聞に連載されていたため、一つ一つの章が短く、テンポよく読める。「美しい日本語」の教科書のような、漱石文学の最高傑作。
【夏目漱石が伝えたいこと】
儒教、封建制、武士道といった高い道徳・倫理観・自制心を尊ぶ「前近代的な精神」は、既に時代遅れとなってしまった。
急激な欧米化、即ち自由・独立・個人主義の台頭により、今後は日本でも個人の自由意思を尊重する時代になっていくだろう。しかし、その代償として、日本人は何らかの孤独に苛まれるはずである。
(自分自身の欲望に個人主義的に素直に従ったのが「私」、私を責めることなく武士道的に潔く死を選んだのがKということになる)。
第33位「ハムレット」シェイクスピア
(新潮文庫)
※福田恆存訳の新潮文庫版か、河合祥一郎訳の角川文庫版がおすすめ!
【どんな本?】
シェイクスピア4大悲劇の一つであり最高傑作。父を毒殺し、母と再婚して王位についた叔父への復讐劇の中で、主人公ハムレットの感情の揺れや迷いを描き出す。「生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ」のセリフでも有名。
悲劇らしく、最終幕に向けて関係者が次々と死んでいき、最後には誰もいなくなる。息をつかせぬ展開に、最後まで一気に読めてしまう。シェイクスピアは欧米の知識人に共通する教養プラットフォームであり、異文化理解のためには必読。
【シェイクスピアが伝えたいこと】
「気高く」生きることを望むならば、人間は徹底的に悩み抜かなければならない。
叔父に父を殺され、王位と母を奪われた青年ハムレットは、理性的にもなりきれず、かといって感情的にもなりきれず悩み続けるが、最期は自分の信じた道を貫き通して復讐を果たす。ハムレットこそ、気高く生きる人間の姿である。
第34位「チーズはどこへ消えた?」S・ジョンソン
(扶桑社BOOKS)
※「変化に対応せよ」というシンプルなメッセージ
【どんな本?】
自分の望むものを手に入れるためには、環境の変化に対応しなければならないと説く実利的な短編寓話。人や組織が環境の変化に直面したときの「あるある」を豊富に提示し、採るべき行動を示唆する。
世界で2800万部、日本で400万部を売り上げた大ベストセラー。多くの大企業で研修に取り入れられているほか、ドジャースの大谷翔平が愛読書として本書を挙げたため、再び注目されている。
【ジョンソンが伝えたいこと】
世の中は常に変化している。その変化に出来るだけ早く気付き、リスクを取って行動を起こさなければ、自分の望むものは手に入らない。さあ、変化を楽しもう。自分を変えよう。
第35位「方法序説」デカルト
【どんな本?】
「神が無条件で正しい、教会が無条件で正しい」という世界観を打ち破り、人間でも思考によって真理にたどり着けることを主張した、まさに近代哲学の第一歩と言える記念すべき一冊。
「我思う、故に我在り」という言葉で端的に示された理性を出発点とする思考法は、近代の哲学のみならず自然科学や社会科学といった学問の礎を成すものであり、教養を身に付けるうえで避けて通れない一冊と言える。
【デカルトが伝えたいこと】
この世の中にある、ありとあらゆる疑わしいものを排除したとしても、その疑っている主体の存在は神ですら否定できない。
この事実は誰でも「そうだ」と言える真理であって、あらゆる思考の第一歩として良いはずである。
第36位「代表的日本人」内村鑑三
【どんな本?】
明治の初めに、日本における代表的なリーダー&インフルエンサーを、聖書との比較で欧米列強に紹介した「徳に基づく日本型リーダーシップ論」。代表的日本人として「西郷隆盛」「上杉鷹山」「二宮尊徳」「中江藤樹」「日蓮」の5人を挙げる。
「日本人の根底に流れる美意識」を理解する上で、同じ明治時代に英語で出版された「武士道」及び「茶の本」と並んで必読の書とされる。アメリカ元大統領ジョン・F・ケネディも愛読。ある日本人記者から「日本で一番尊敬する政治家は」と質問されたケネディは「Yozan Uesugi」と答えて日本人を驚かせた。
【内村鑑三が伝えたいこと】
欧米の皆さん!日本にもこんなに素晴らしい「徳に基づくリーダー」がいますよ!どうか分かってください!
第37位「オイディプス王」ソポクレス
(光文社古典新訳文庫)
※「出生に関する衝撃的な秘密」を抱えたオイディプスが自分の運命を向き合う悲劇
【どんな本?】
古代ギリシャ三大悲劇詩人の一人であるソポクレスが、紀元前427年ごろに書いた悲劇。人は運命にどう向き合うべきかを、壮大な世界観の中で精緻に描き出す。
アリストテレスが悲劇における最高傑作の例として挙げており、父殺し・近親相姦・出生の秘密等、悲劇的要素がふんだんに詰まっている。フロイトが提唱した「エディプス・コンプレックス*」の語源。欧米知識人の間で共有されている教養の一部となっている一冊。
*エディプス・コンプレックス
男児が無意識のうちに同性である父を憎み、母を性的に思慕する傾向のこと。エディプスはオイディプスのドイツ語読み。
【ソポクレスが伝えたいこと】
※ネタバレありです
主人公オイディプスは、先王殺害の真犯人を探究していった結果、「父を殺して母を妻とする」という神託の予言が知らぬ間に実現しているという恐るべき真実を発見する。
過去にどれだけ英雄的な行為を為したとしても、些細な言い争いから衝動的に老人を殺したり、占い師から不都合な事実を突きつけられて感情的に怒りをぶちまけたり、真実を見ようとせず短絡的に身内を死刑にしようとしたりするような傲慢で軽率な人間に待っているのは、悲劇的結末のみである。
人間は運命と向き合わなければならないのだ。
第38位「人生論」トルストイ
【どんな本?】
ロシアの文豪トルストイが、人間が生きる意味を「幸福への志向」と定義した晩年の書。動物的自我を否定し、愛という人間固有の理性的活動で周囲を愛することにしか、人が生きる意味は無いとする。
「理性の力で幸福になる」という、極めてヨーロッパ的な考え方を学ぶ上でも最適な一冊。普段忙しく、心がなんだか乾いているなと思う人に特におすすめ。
【トルストイ が伝えたいこと】
科学は人間を自然の一部と位置付けたがる。その方が説明が簡単だからだ。しかし、結局この世は人間の視点でしか認識できないのだから、理性を中心に据えてどう生きるかを考えるべきである。
人間が動物のように一時の快楽を追い求めたり、そのために争ったり、死を恐れたりしていては、幸福にはなれない。人間は時間と空間を超えた理性的意識に従って、自分を愛し、他者を愛し、自分以外のすべての幸福を願う事で、真の幸福を得ることができる。そうすれば、死への恐怖は永遠の生へと変わる。
第39位「生きがいについて」神谷美恵子
【どんな本?】
ハンセン病施設で医療活動に従事した精神科医神谷美恵子が、苦しみや悲しみの底にあっても、なお朽ちない希望や尊厳を患者の中から見出す。そして、健康な者に「生きる意味」を問う。日常への感謝、充実感、生きる力が内側から湧いてくる一冊。
【神谷美恵子が伝えたいこと】
人は通常の日常生活が送れなくなると、切実な必要に追いやられて、「生きるとは何か」「何を生きがいとするか」を問う精神世界に基盤を置くようになる。
自分は天に必要とされていて、忠実に生きぬく責任があるのだという使命感を感じ、何かに打ち込むところまで達すると、人は前向きに生きられるようになる。人間の存在意義は、決してその利用価値や有用性によるものではない。私たちにできることは、絶えず新たに光を求め続けることだけである。
第40位「超入門 失敗の本質」鈴木博毅
【どんな本?】
歴史的名著「失敗の本質~日本軍の組織論的研究~」の入門編。太平洋戦争開戦後の日本の「戦い方」を対象として、組織としての日本軍の失敗を分析する。「ゲームのルールを変える主体」vs「既存の土俵で戦い続ける主体」の構図は、ビジネスにもそのまま当てはまる普遍性あり。
【鈴木博毅が伝えたいこと】
旧日本軍が太平洋戦争に負けた主要因は、次のような点である。
・大戦略が欠如していた
・既存の枠組みにとらわれ、ルールチェンジに対応できなかった
・空気を読みあうような硬直的な組織だった
・大本営と現場の距離が遠かった
第41位「ソクラテスの弁明」プラトン
(光文社古典新訳文庫)
※ソクラテスの裁判の様子を、弟子のプラトンが生き生きと描き出す古典の名著!
【どんな本?】
古代ギリシャの哲学者ソクラテスが、裁判の被告の立場から「自分がアテナイで展開してきた哲学対話は何であったか」「何故そのようなことをしたのか」について語った様子を、弟子のプラトン(当時28歳)が記録したもの。
ソクラテスが反対尋問で論理を積み重ねていく様子は見事であり、哲学や論理学に関心のある人にとっては必読の書。約2400年前に書かれたものとは思えないくらい、整然とストーリーが展開する。
【ソクラテスが伝えたいこと】
私の友人がデルフォイで「ソクラテス以上の知者はいない」という神託を受けた。一方、私は「神が間違いを言うはずがない」という信念のもと、自分より優れた知者を探すが、皆、自分は知者であると言うものの、実際大切なことは何も知らない。
そこで私は、同じ無知であれば、無知であることを自覚している自分の方が知者であるということに気が付いたのである(いわゆる「無知の知」)。
第42位「茶の本」岡倉天心
【どんな本?】
明治の中頃、「茶道」を主題に、「日本人の高い精神性」「謙虚さ」「自然とシンプルさを愛する東洋的な心」を欧米に紹介した日本の文化論。
「日本人の根底に流れる美意識」を理解する上で、同じ明治時代に英語で出版された「武士道」及び「代表的日本人」と並んで必読の書とされる。欧米人にも大きな反響をもたらした一冊。
【岡倉天心が伝えたいこと】
アジアで生まれた茶の文化は、全世界に敬意を持って受け入れられた、唯一の東洋の儀礼である。茶という面において、東洋は明確に西洋より優れている。
茶の文化は、質素さ、謙虚さ、繊細さなどに価値を置くという面で、日本人の精神に深く影響を与えているのだ。
第43位「ブッダのことば(スッタニパータ)」釈迦
(岩波文庫)
※仏教最古の古典だが、宗教というより道徳論や修身論の趣き
【どんな本?】
数ある仏教の経典の中では最古であり、釈迦の思想を最も正確に後世に伝えるとされる経典集。スッタは「経」、ニパータは「集まり」の意味。仏教思想の源泉を知るのに最適の一冊。
東洋における教養の教科書。後世への影響は計り知れない。どのような教養を身に付けるにせよ、東洋人である限り、本書と「論語」は必読の入門書。現在の仏教の教義は複雑だが、釈迦が語った仏教の神髄は非常にシンプルなので、すっと心に落ちてくる。
【釈迦が伝えたいこと】
あらゆる現象や物質は独立した実体を持たず、無限の関係性の中で絶えず変化する。財産・名誉・健康・愛する人との関係等々、確かなものなど一つもない。
自己を制御し、あらゆるものへの執着、すなわち煩悩を捨て、極端を避けて中道を生きる者は、その言葉・心・行為によって苦悩から離れ、永遠の輪廻地獄から脱し、不死・平安・不滅なるニルヴァーナ(涅槃)の境地に達することができる。
※現代の大乗仏教にみられる偶像崇拝や祈祷・念仏の類について、釈迦は一切語っていない
第44位「フランクリン自伝」フランクリン
【どんな本?】
アメリカ建国の父、ベンジャミン・フランクリンの自伝。自己啓発本の元祖。勤勉・倹約、科学的探究心、合理主義でいかに自分は成功したかを説く「おじさんの自慢話」ジャンルの最高峰。自ら「人生をやり直せると言われても、私は自分の生涯を全部そのまま繰返したい」と評する自信っぷり。
人徳を完成させるための「13の徳目」が本書の肝。「アメリカ人が尊敬するアメリカ人とは、どのような人物なのか」がよく分かる一冊であり、アメリカ研究でも用いられる。アメリカという国や国民性を理解する上では、本書、「アメリカにおけるデモクラシーについて」「プラグマティズム」の3冊は必読。
【フランクリンが伝えたいこと】
節制・勤勉・誠実・謙虚といった「人徳」を身に付けた者こそが、社会の役に立てる。
第45位「昭和16年夏の敗戦」猪瀬直樹
【どんな本?】
首相直轄の「総力戦研究所」は対英米戦のシミュレーションで日本必敗を結論付けていたにもかかわらず、なぜ日本は戦争への道を進んでいったのか。主に開戦直前の半年を描き出すノンフィクション作品。
薄い文庫本なので、一気に読んでしまえる。若手エリート官僚同士の熱いぶつかり合いや、日本という国が誤った判断を下していく過程を生々しく描き出し、日本的組織の構造的欠陥を暴く。作者は元東京都知事の猪瀬直樹氏。シンプルに、面白い本。
【猪瀬直樹が伝えたいこと】
日本政府が開戦決定へと至ったプロセスと並行して、政府は日本必敗の結論を得ていた。日本人全員が軍国主義で頭がおかしかったわけでも、軍部だけが独走したわけでも、能力的に劣っていたわけでもない。
研究所の結論は若手がしがらみのない中で得たもので正確だった一方、報告を受けた内閣は全員が組織の代弁者であり、誰も責任を取ろうとしなかったのだ。
第46位「マネジメント」ドラッカー
(ダイヤモンド社)
※経営学の古典中の古典。全てのビジネスパーソン必読の書!
(新潮文庫)
※いわゆる「もしドラ」。ドラッカー初心者はこちらからでも!
【どんな本?】
現代経営学の巨匠ドラッカーが、人間がいきいきと働き、社会に貢献できる組織とは何かを深く考え、初心者向けに一冊にまとめた入門書&教科書。マネジメントの要素を論理的に分割・分類して、一つずつ丁寧に解説する。
ドラッカー初心者は、まず本書で組織マネジメントの理論的基礎を、そして「プロフェッショナルの条件」で自己マネジメントの理論的基礎を学ぶのが一般的。
経営学に馴染みのない方は、本書の代わりに漫画「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」がオススメ。本書は「もしドラ」と呼ばれ、2011年には元AKB48の前田敦子主演で映画化された。
【ドラッカーが伝えたいこと】
現代社会では、主な社会的課題は組織の手に委ねられており、組織を率いるマネージャは社会のリーダー的な階層にある。この組織に成果をあげさせるための手段・機能がマネジメントである。
マネジメントの対象は顧客や市場にとっての価値という「成果」であって、社員ではない。マネジャーは、一人ひとりの強みと知識を生産的なものとし、働き甲斐と自主性を持たせ、成果に繋げなければならない。
第47位「文明論之概略」福沢諭吉
【どんな本?】
明治初期、日本が欧米列強に伍して独立を守っていくには、理想はともかく、現実論として何が必要かを説いた渾身の一冊。まず最初に「人類の目指すべき最大の目的」としての文明の姿が語られ、福澤の大局観が炸裂する。福澤の著書の中では、最も学問的な体裁が整っていると言われている。
大局観と先見性を持って、言いにくいこともどんどんぶった切っていく福澤に、読んでいて気持ちがスカっとする一冊。慶應受験者はもちろん、教養を志す全ての人にとって「学問のすすめ」「文明論之概略」「福翁自伝」の3冊は特に必読。
【福沢諭吉が伝えたいこと】
日本は「徳」の分野では西洋に負けていないが、文明・学問・技術という「才(=智恵)」では完敗している。日本人は徳川幕府にいいように飼い慣らされてしまい、独立自尊の気概がない。
攘夷も軍拡も国体論もキリスト教も儒教も役に立たない。早急に国民が智恵を付け、西洋文明に追い付かねば、日本の独立は危うい。一国の独立など、人間の智徳からすれば些細な事柄だが、現実の国際政治の有様では、そこまで高遠な議論はできないのだ。
第48位「ニコマコス倫理学」アリストテレス
(光文社古典新訳文庫)
※倫理学の古典最高峰!エッセイのようなので挫折せず読める
【どんな本?】
万学の祖アリストテレスが「善く生きるためには何をすべきか」を突き詰めた実学の書。歴史上初めて「倫理学」を体系化した書としても知られる。プラトンのイデア論(観念論)やエロス論(完全への渇望)に対するアンチテーゼでもある。
本書で示される「徳は科学ではないので定量化できないが、両極端の間のどこかに存在する」という「中庸」の考え方は、東洋の釈迦や孔子も言及していることで有名。2500年の歴史を乗り越えて受け継がれてきた普遍的かつ不変的な人生の要諦であり、基礎的教養の一つとして学んでおくべき。
【アリストテレスが伝えたいこと】
「人はどう生きるべきか」という幸福・道徳・倫理に関わる分野は(数学や天文学と異なり)何らかの法則が普遍的に当てはまるということはなく、「大抵において成り立つ」くらいの程度で理解した方がよい。明確なイデア(理想)など存在しない。
それ故、理論研究には意味が無い。自らの努力によって得た「徳(人格)」を実践し、「最高善」を目指すことこそが、人生の究極の目的である「幸福」をもたらす。
幸福が究極の目的である理由は、私たちが幸福を望むのは幸福それ自体のためであって、決して他のためではないからである。人間の幸福は、快楽・財産・名誉からはもたらされない。何故ならそれらは単に幸福を得るための手段であって、目的ではないからだ。
第49位「自助論」スマイルズ
【どんな本?】
欧米人300人の成功談を集めた自己啓発本の古典。序文の「天は自ら助くる者を助く(Heaven helps those who help themselves)」という言葉が特に有名。日本では「西国立志編」という名前で発刊され、福澤諭吉の「学問のすすめ」と並んで「独立自尊を説く書」として読まれた。
「世界最古の自己啓発本」「あらゆる自己啓発本のルーツ」とされることも多い。トヨタグループの創始者である豊田佐吉や、サッカー元日本代表の本田圭佑も愛読。
【スマイルズが伝えたいこと】
財産も地位も天賦の才能もない人間でも、他人に頼らず独力で、勤勉と節約によって成功できる!
第50位「幸福論」ラッセル
【どんな本?】
ヒルティ『幸福論』、アラン『幸福論』、と並ぶ、いわゆる「3大幸福論」の一つ。第一部で回避すべき「不幸の源泉」を、第二部で追うべき「幸福の源泉」を説明する、三大幸福論の中で、最も論理的な作品。
どのような不幸をどのように回避し、どのような幸福をどのように追えばよいかを「心」ではなく「頭」で理解できる。ノーベル文学賞も受賞した作者が送る、21世紀の英知の代表例とも言える一冊。
【ラッセルが伝えたいこと】
幸福は、ごく少数の例外を除き、自然に手に入るものではない。人は自発的かつ主体的に不幸を「回避」し、幸福を「獲得」しなければならない。
特に仕事は大切である。熱意を持って社会に役立つ仕事をし、それに健全な誇りを持つことが、幸福の直接の源泉となる。
逆にこの世の不幸を産み出す源泉は「悲観主義」「競争」「過度の刺激」「精神的疲労」「嫉妬」「罪悪感」「過度な自意識」そして「世間からの評価」である。特に避けるべき最大のものは「過度な自意識」だ。
.png)