「アメリカにおけるデモクラシーについて」
アレクシ・ド・トクヴィル
基本情報
初版 1835年
出版社 中央公論新社
難易度 ★★★★☆
オススメ度★★★★☆
ページ数 178ページ
所要時間 2時間30分
どんな本?
数多くの欠陥を抱えながらも、「一部の知識階級が蒙昧な民衆を支配する」というヨーロッパの常識を打ち破り、民衆自身が自由と権利を実現して国力を高めるアメリカの強さを分析した歴史的名著。
時にトランプのような奇抜な大統領を生み出し、右に左にフラフラ揺れながらも、なぜアメリカは世界No1であり続けられるのか、建国の歴史からその秘密に迫る。
アメリカという国や国民性を理解する上では、本書、「プラグマティズム」「フランクリン自伝」の3冊は必読。
著者が伝えたいこと
デモクラシー(多数派支配の民主主義)は構造的欠陥を多数持つが、全体としてそれ以上の「成果」を出すことができる。
アメリカのデモクラシーに貢献している要素は主に以下の3つであり、影響力は(1)<(2)<(3)である。
(1)建国の諸条件
身分差のない平等さ、開拓で得た独立心、成功欲、権利意識
(2)法制の影響
連邦制、地方自治の諸制度、司法制度(特に陪審制度)
(3)習俗
政教分離、実利重視、政治への参加による経験教育

著者
アレクシ・ド・トクヴィル
Alexis de Tocqueville
1805-1859

フランスの政治家、政治思想家。ノルマンディー地方の貴族出身。下院議員 (1839)、憲法議会議員 (1848)、外務大臣 (1849)を歴任。ナポレオン3世のクーデターに反対して逮捕。政界を退く。
1831年から米国を視察。近代デモクラシー社会を歴史的必然ととらえ、アメリカの強さの秘訣を自由や平等の観念から考察した。
こんな人におすすめ
アメリカの強さの神髄を理解したい人。19世紀のヨーロッパ人がアメリカをどう見ていたかに関心のある人。
書評
論旨は明快だが、18~19世紀の知識人の著作にありがちな回りくどさは否めない。もったいぶって論理を振り回す傾向があるのはフランス人らしい。
よって、本書を読破するにあたっては、目先の難解さに惑わされず、話のスジをしっかり追うという態度が求められる。
歴史のおさらい
1776年 アメリカ独立宣言
1789年 フランス革命
1804年 ナポレオンが皇帝に即位
1814年 ウィーン会議
1823年 モンロー宣言
1829年 アンドリュー・ジャクソン大統領就任(~37年)
1830年 フランス7月革命(ブルボン復古王政崩壊)
1831年 トクヴィルがアメリカを旅行
1835年 『アメリカのデモクラシー(第一巻)』発刊
1840年 『アメリカのデモクラシー(第二巻)』発刊
1848年 フランス2月革命(ルイ・フィリップ王政崩壊)
1852年 ナポレオン3世即位
1853年 ペリー、浦賀に来航
1861年 アメリカ南北戦争
(中公クラシックス)
※原書の最重要部分(第2部第6~9章)を抜き出した抄訳
(岩波文庫)
※原書の全体訳。アメリカの強さの秘密に迫る名著
要約・あらすじ
※本書(中央公論新書版)は、トクヴィル著「アメリカにおけるデモクラシーについて」の最重要部分(第2部第6~9章)を抜き出し、抄訳したものです。全体を読まれたい方は岩波書店版をご参照ください。
第6章「アメリカ社会が民主制から引き出す真の利点」
■アメリカの政治や社会を特徴付けているものは、諸階層の「平等」である。
■欧州では、土地の所有と相続に基づく身分制が長らく続いた。優秀な貴族政治家が、蒙昧な民衆を導いた。しかし、近年の銃器と印刷術の発展や新大陸の発見は、貴族と平民の立場・知識・経済力を平準化する方向に働いた。
| 政治家 | 民衆 | |
| 貴族政治 | 優秀 | 蒙昧 |
| 民主政治 | それなり | それなり |
■貴族と農奴の間には身分・能力・経済力に絶対的な差があったため、互いに「それ相応に、自制心を持って」向き合った。しかしデモクラシーでは、全員が平等であり、そこに自制はない。同時にその欠点を補う仕組みもないのだが、現時点では唯一アメリカだけ、デモクラシーが機能している。
■その理由は「試行錯誤が可能なこと」だ。政治がうまくいかなければ、政権を交代させればよい。デモクラシー下の民衆は、それを判断できる程度の能力は持っている。公務員が腐敗しても、それは階級間の対立にはならず、個人の問題に留まる。これは王政や貴族政治では不可能なことだ。
■アメリカでは個人の権利や法律がよく守られている。まず、欧州と異なり民衆に参政権が付与されているので、他人の権利を奪おうという動きがない。また、各種法律には自分たちの権利が反映されており、自分たちの意思で変更可能であると信じているから、破られることも少ない。人は自分と同等である人に対して付与した命令権に従うことに、それが仮に最下級の役人であっても、抵抗を感じない。
■一般民衆が参加する政治活動も盛んである。政治に介入し、政治を論ずることは、アメリカ人の最大の関心事であり、いわば唯一の楽しみである。個人としては徳が高いわけではないが、政治に参加することで公共の仕事を知り、社会に啓蒙されるのである。
■しかし民主的自由が、優れた政府を生むわけではない。民主政治は衆愚政治と表裏一体であって、寡占政府の方が一貫性・持久力・大局観・洗練された徳の実現・他国への良い影響等でよっぽど優れている。結局のところ、アメリカの強さは民主政治が生んだ「人」の活力そのものなのである。
第7章「アメリカにおける多数派の万能とその諸結果について」
■デモクラシーにおいて、多数支配の絶対性は三権すべてにわたっており、その本質であると言える。多数派が唯一の主体であって、欧州に見られる貴族と民衆の緊張関係のような相互牽制の仕組みはない。
■加えて、議員や政権が年によって変わるため、政治は不安定である。しかし人々はそれにより「最大多数の幸福」が実現されると信じている。
第8章「アメリカにおいて多数の圧政を緩和するものについて」
■多数派による圧政を抑止できる主体があるとすれば、それは法曹集団だろう。彼らは秩序・論理・形式を重んじるという点で貴族的であるし、米英特有の(文字にならない)慣習法を理解できる唯一の集団だからだ。
■また、陪審員が一般人から任命され、国民の一部が法執行に携わるという点も、多数派の圧制に対する牽制になっている。アメリカ人の実学的な知性と政治的良識は、この陪審制度によって培われている。
第9章「アメリカにおいて民主的共和制を維持する傾向を持つ諸要因について」
■キリスト教的な道徳は、家庭生活を安定させ、社会も平和で秩序立ったものになる。政治と宗教は分離されており、ヨーロッパで見られる権力闘争の類も避けられている。
■アメリカ人は非常に実利的であって、「普遍的な観念」からは遠い。よって、実務には強いが、文学・詩・歴史の大家は生まれてこない。
学びのポイント
民主主義が生み出す「人」にこそ競争力がある
民主的自由が、優れた政府を生むわけではない。民主政治は衆愚政治と表裏一体であって、寡占政府の方が一貫性・持久力・大局観・洗練された徳の実現・他国への良い影響等でよっぽど優れている。
結局のところ、アメリカの強さは民主政治が生んだ「人」の活力そのものなのである。(要約)

民主政府自体は、たいして能力も徳も高くない民衆が選んだ人物が運営するのであって、寡占政府より立派でも効率が良いわけでもない。
ただ、民主政治下においては、民衆は積極的に政治に参加し、法と個人の権利が守られた中で各自の利益が最大になるように経済活動に勤しむ。このことが、活力のある「人」を生み出し、国全体も力を持つようになる、ということをトクヴィルは言っている。
ここで思い出しておきたいのが、第二次世界大戦中のイギリス首相チャーチルのこの言葉だ。ヒトラーの全体主義と戦ったチャーチルの言葉だからこそ、民主主義への秘めたる自信を窺うことができる。
民主主義は最悪の政治形態らしい。ただし、これまでに試されたすべての形態を別にすればの話であるが。
It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.
確かに、独裁主義や貴族政治では、民衆には自由は与えられず、ただお上から与えられた法律に従い、創意工夫をするでもなく、日々を過ごすだけで、そこに活力や成長を見出すことは難しい。
その極端な例が共産主義だろう。「能力に応じて働き、必要に応じて受け取る」仕組みだが、人間はそこまで理性的ではない。「働かずに、受け取りたい」人々の存在により、労働生産性は落ち、資本主義&民主主義の前に敗れることとなる。
政治体制が作る「人」に着目したという点で、トクヴィルの考察は興味深いものになっている。
アメリカ的デモクラシーの強さ
幾世紀も経てば、アメリカに植民したイギリス人の子孫が種々に分かれて、共通の相貌を示さなくなるであろう。しかし、新世界に諸階層の恒久的な不平等が樹立される時期を予見することができない。
平和か戦争か、自由か圧政か、繁栄か貧困かによって、イギリス系アメリカ人という大家族の種々の末裔の運命にいかなる相違が生じようと、少なくとも現在に似た社会状態が維持され、そこから流れ出る慣行と理念とを共有するであろう。

現在も、トクヴィルの予見どおり、アメリカは民主主義を守り続け、個人の権利と言う意味での「恒久的な不平等」は維持されている。
南北戦争という内戦以降、アメリカは一度も戦争に負けることなく平和を維持し続けた。憲法はこまめに変更されているが、政体は一切変わらず、自由も守られている。
一方、デモクラシーとは異なる土俵にある「資本主義」が、トクヴィルの言う「繁栄か貧困か」という不平等を生み出した。アメリカの格差は先進国の中でも圧倒的に高く、ここ最近でも上昇を続けている。
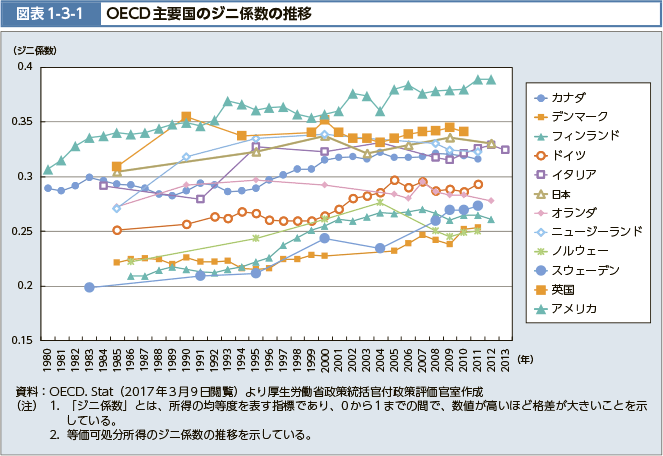
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/backdata/01-01-03-01.html
通常、平均よりも収入や能力の低い集団が、利権や富の平等化を求めて、政党を作るなり内乱を起こすなりする。それは歴史が証明しているし、アメリカの歴史家ウィリアム・ダラントは著書『歴史の大局を見渡す』で、こんな風に言っている。
経済力が平均以下の者だけが平等を求め、自分の優れた能力に気づいている者は自由を求める。そして最後は能力のある者が意のままにする。
アメリカは格差が激しく、上位1%に総資産の3割が集まっているとも言われている。これほどの格差が生じれば、革命なり内乱が起きそうなものだが、アメリカの場合は権利や機会の平等は担保されているので、再分配論が起こりにくいのであろう。
あるいは、お金をうまく使える人に集めておくことで、経済は活性化し、国力も強まり、結果として自分も受益するなら、それでいいと達観しているのかもしれない。
ちなみに、NHKが放送した「ハーバード白熱教室」で話題となったマイケル・サンデル教授は、著書『これからの「正義」の話をしよう』で、ジョン・ロールズの「無知のベール」仮説を紹介している。
ロールズは「自分の立場(財産の多寡、宗教、民族、性別等)は不明」という「無知のベール」を被り、いわば純粋な初期状態であるべき社会の仕組みを問うと、以下2つの正義の原理が導き出されるとした。
①言論の自由や信教の自由といった基本的自由をすべての人に平等に与える(多数派が利する功利主義の拒否)
②所得と富の平等な分配を求めるものの、社会で最も不遇な立場にある人びとの利益になるような社会的・経済的不平等のみを認める(自由至上主義であるリバタリアニズムの拒否)
つまり、現実には貧乏な人が平等を求め、能力に恵まれた人が自由を求めるのだが、仮に「自分の立場は不明」としたうえで、どのような社会が良いかを尋ねると、人は(自分が裕福なのか貧乏なのか、能力があるのかないのか分からないので)「平等」と「自由」の双方を求めるということ。これはこれで、非常に興味深い。
人事部長のつぶやき
高学歴者の特性
法律を専門に学んだ人々は、その勉強から秩序を重んずる習性と、形式に従う風儀と、論理の一貫性に対する一種の本能的な愛情を汲み取っている。
これは全て官僚の特性と重なる。これは私見だが、一般企業でも、いわゆる高学歴者にはこの傾向が強く、「形式と論理」に拘泥することが多いような気がする。
例えば仕事上、何らかの手続きを廃止するだけのことに「以前は○○という事情があって妥当だったが、昨今は○○という状況変化があることを踏まえ・・・」のような、一貫性保持のためのシナリオをいちいち考えるようなこと。
このような人々は、「ロジック」的判断には長けているが、真善美を直観で見抜くような「アート」的判断も同時に長けているかと言えば、必ずしもそうではない。

これも私見ですが、ロジック型人間はせいぜい課長どまり。それ以上の責務を負うには、秩序・形式・論理だけでは立ち行かなくなるでしょう!
(中公クラシックス)
※原書の最重要部分(第2部第6~9章)を抜き出した抄訳
(岩波文庫)
※原書の全体訳。アメリカの強さの秘密に迫る名著
.png)


