「ハムレット」
W.シェイクスピア
基本情報
初版 1599-1602年(イギリス)
出版社 角川文庫、新潮社等
難易度 ★★★☆☆
オススメ度★★★★☆
ページ数 284ページ
所要時間 3時間30分
※以下、ネタバレありです。結末を知らずに読みたい方はご注意ください!
どんな本?
シェイクスピア4大悲劇の一つであり最高傑作。父を毒殺し、母と再婚して王位についた叔父への復讐劇の中で、主人公ハムレットの感情の揺れや迷いを描き出す。「生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ」のセリフでも有名。
悲劇らしく、最終幕に向けて関係者が次々と死んでいき、最後には誰もいなくなる。息をつかせぬ展開に、最後まで一気に読めてしまう。シェイクスピアは欧米の知識人に共通する教養プラットフォームであり、異文化理解のためには必読。
著者が伝えたいこと
「気高く」生きることを望むならば、人間は徹底的に悩み抜かなければならない。
叔父に父を殺され、王位と母を奪われた青年ハムレットは、理性的にもなりきれず、かといって感情的にもなりきれず悩み続けるが、最期は自分の信じた道を貫き通して復讐を果たす。ハムレットこそ、気高く生きる人間の姿である。

著者
ウィリアム・シェイクスピア
William Shakespeare
1564-1616

イギリスの詩人、劇作家。ストラトフォード・アポン・エーボンに裕福な商人の長男として生れるが、父が没落したため高等教育は受けなかった。
18歳のとき8歳年長のアン・ハサウェーと結婚し、1男2女をもうける。その後の子細な記録は残っていないが、20歳過ぎにロンドンに出たらしく、1592年には新進の劇作家兼俳優として著名となった。
1613年頃に引退するまでの約20年間に、「ロミオとジュリエット」「ヴェニスの商人」のほか、「ハムレット」「オセロ」「リア王」「マクベス」の四大悲劇を含む約40の傑作を残した。晩年はロンドンを去り、平和で平凡な余生を終えたとされる。
こんな人にオススメ
シェイクスピアを初めて読む人、舞台・演劇に関心のある人
書評
シェイクスピア4大悲劇の一つであり、ストーリー、登場人物の個性、愛憎・嫉妬・憐み等の心理描写などなど、総合的な完成度が非常に高い作品となっている。
また、基本的には分かりやすい「復讐劇」であり、初演当時の時代背景やキリスト教に関する知識がなくとも楽しめる普遍性を持っているため、初演から400年たった今でも世界中で公演される不朽の名作となっている。
なお、日本語訳の定番と言えば、新潮社の福田恆存訳が挙げられるが、若干古めかしい。最近では、NHK100分de名著でハムレットを解説した東大大学院教授の河合祥一郎が、野村萬斎から依頼されて舞台用に翻訳したものが角川文庫から出版されている。こちらはリズムや響きが非常に滑らかで、日本語として非常に読みやすい。
(新潮文庫)
※福田恆存訳の新潮文庫版か、河合祥一郎訳の角川文庫版がおすすめ!
要約・あらすじ
.jpg)
第1幕~ハムレット、復讐を決意~
■デンマーク王が急死すると、その弟であるクローディアスが王位を継ぐとともに、王妃ガートルードをそのまま自分の妻とする。デンマーク王の息子ハムレットはそれに納得がいかない。
■友人ホレイシオから「死んだデンマーク王の亡霊が出る」という話を聞きつけたハムレットは、実際に父親の亡霊と対面し、「私は現王のクローディアスに毒殺された。復讐せよ」と言われる。
■復讐を誓うハムレットは、狂気を装いながら、その時を窺うことにする。
第2幕~交錯する思い~
■宰相ポローニアスの娘オフィーリアは、父から命じられたとおり、ハムレットからの恋の誘いを断る。するとハムレットは半狂乱の状態に陥ったため、ポローニアスは、それを現王クローディアスに報告する。
■しかし、ハムレットの様子がおかしいのは、父王の死と早すぎた母の再婚によるものと考えていた王と王妃は、ポローニアスの言葉を信じない。そこでポローニアスは「オフィーリアとハムレットを引き合わせ、それを隠れて見てみよう」と王に提案する。
■一方のハムレットは、王に毒殺の場面を含む芝居を見せ、その反応を確かめようと決める。
第3幕~生きるべきか、死ぬべきか~
■ハムレットは「生きるべきか、死ぬべきか」と自問自答する。父と母と王座を奪われるという恥辱に耐えて生きるか、クローディアスに復讐して自分も死ぬか。気高く生きるには、どちらを選ぶべきなのか、深く悩む。
■父ポローニアスから指示を受けたオフィーリアは、偶然を装ってハムレットと対面し、別れを告げる。既に復讐を決意しているハムレットは、オフィーリアに「尼寺へ行け」と、自分から離れて純潔を守るように言いつける。それを陰から見ていたクローディアスは、ハムレットが自分に復讐を企てていることを確信し、ハムレットをイギリスに送ることを決める。
■毒殺の場面を含む芝居を観たクローディアスは狼狽し、席を立つ。それを見たハムレットは、クローディアスこそが父を殺した張本人であることを悟る。
■ハムレットは、クローディアスが跪き、懺悔している背後を取る。しかし、懺悔している最中に殺すと、クローディアスは地獄ではなく天国に行ってしまう。そのためハムレットは復讐を思いとどまるが、クローディアスの懺悔は形だけで、実は本心からではなかった。
■母ガートルードから呼び出されたハムレットは、陰に隠れて会話を聞いていた宰相ポローニアスをクローディアスと間違えて刺し殺す。そして母の裏切りを徹底的に詰るが、当のガートルードは罪の意識を感じておらず、会話は完全にすれ違う。
第4幕~悲劇の始まり~
■ノルウェー王フォーティンブラスは父を前デンマーク王(=ハムレットの父)に殺されているが、復讐を企てることなく、名誉のためにデンマーク領を通過してポーランド領に攻め入る。その姿を見たハムレットは、復讐することも気高く生きることも何も出来ない自分にいら立つ。
■一方、クローディアスはイギリス王にハムレットを殺すように要請する。しかし、イギリスへの航海の途中でその依頼状を発見したハムレットは、自分ではなく王の廷臣2名を殺す内容に書き換えた上で、単独でデンマークに帰国する。
■そこでクローディアスは、父親であるポローニアスをハムレットに殺されたレアティーズをそそのかし、ハムレットと剣術で勝負させるように仕向ける。激情するレアティーズは剣先に毒を塗り、王は念を入れてハムレットの飲み物にも毒物を混入させる。
■その企ての最中、オフィーリアが度重なる悲しみのあまり狂い、溺死したとの知らせが舞い込み、レアティーズは改めてハムレットへの復讐を決意する。
第5幕~そして誰もいなくなった~
■ハムレットはオフィーリア埋葬の場面に出くわし、レアティーズと揉み合いになる。王の廷臣たちが直ちに止めに入るが、ハムレットは怒りの発作が収まらない。
■ハムレットとレアティーズの剣術試合が始まる。まず王妃が毒入りと知らずに酒を飲んで死ぬ。レアティーズの毒剣は途中でハムレットの剣と入れ替わり、両者ともに毒剣の刃に倒れる。そして、死に瀕するレアティーズからクローディアスが全ての黒幕であることを聞いたハムレットは、クローディアスを殺す。
■そこにポーランドからフォーティンブラスが凱旋してくる。デンマーク王の血筋が途絶えた今、フォーティンブラスは新デンマーク王となる取り決めだった。ハムレットは自分の為したこととその大義を語り継ぐように、友人ホレイシオに言い残して、死んでいく。
学びのポイント
弱き者よ、汝の名は女なり
亡くなってわずか二か月で──いや、二か月さえ経っていない。
(私の父は)立派な王だった。今の王は獣のような奴だが、太陽の神のような人だった。あんなに母上を愛し、天から訪れる風が母上の顔に強く当たるのさえ許さぬほどだったのに。なんということだ、忘れることはできぬのか。
母上にしても、ああ、父上の愛をむさぼるように受けて、しがみついていたではないか。それが、ひと月足らずで──考えたくない。──弱き者、汝の名は女──
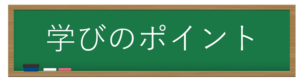
この場面は本作品の冒頭、ハムレットによる初めての「独白」で現れる。死んだ父を讃え上げ、そしてその王位を奪った叔父がいかに劣っているかに毒づいた後、ハムレットの怒りの矛先は母親に向かう。
当時は男尊女卑の時代で、例えば聖書には「妻たる者よ。主に仕えるように自分の夫に仕えなさい」とある。しかしハムレットの母親は、父の死後、わずかな期間を置いただけで叔父と再婚してしまう。ハムレットにはそれが許せない。
当初は「たった二か月で」と言っているのに、いつの間にか「ひと月足らずで」と短くなってしまっているあたりに、ハムレットの憤激が読み取れる。
ではなぜ、「弱き者、汝の名はガートルード」ではなく、「汝の名は女」と一般化されているのであろうか。
後々の場面で、ハムレットから「なぜ父を裏切るようなことをしたのか」と責められた際、ガートルードは「私が何をしたというのです」と言ってのける。つまり、ガートルードにとってクローディアスとの再婚には何らの罪の意識もない。
加えて、結果的に、ガートルードはクローディアスが先王を殺したことを知らないままハムレットの狂気を心配し、王とレアティーズの謀略でハムレットの命が狙われていることも知らず、最後には自分に毒杯が盛られていることも知らずに死んでゆく。
自分の罪にも自分の身の回りで何が起きているかも気付かないガートルードを見たハムレットは、「女性とは往々にしてこんなものだ」と普遍化して「汝の名は女」と言った。ここにも、エリザベス処女王の時代における男尊女卑的な思想が見て取れる。
生きるべきか、死ぬべきか
生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ。
どちらが気高い心にふさわしいのか。
非道な運命の矢弾をじっと耐え忍ぶか、
それとも怒濤の苦難に斬りかかり、戦って相果てるか。
To be or not to be, that is the question;Whether ’tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles
And, by opposing, end them.
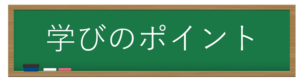
これは「ハムレット」のみならず、シェイクスピア作品全体を通じて最も有名なフレーズと言えるだろう。
この場面は過去、様々な翻訳家によって様々に訳されてきた。例えば坪内逍遥は「世に存る、世に存らぬ、それが疑問ぢゃ」、福田恆存は「生か、死か、それが疑問だ」などとしてきたが、ここだけを見ていては本当の意味は分からない。To be or not to be に続く対比構造まで見る必要がある。
生きるべき=非道な運命の矢弾をじっと耐え忍ぶ(=叔父に復讐しない)
死ぬべき=怒濤の苦難に斬りかかり、戦って相果てる(=叔父に復讐する)
これはつまり、叔父に父親と母親と王座を奪われるという恥辱(=非道な運命の矢弾)をじっと耐え抜くか、それとも「復讐」を果たして叔父を殺し、自分も死んでいくか、気高く生きるにはどちらを選択すべきかと悩んでいるのである。
ちなみに、キリスト教では以下のとおり「復讐」は固く禁じられており、ハムレットはその観点からも煩悶することになる。
愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。「『復讐はわたしのすること、わたしが報復する』と主は言われる」と書いてあります。
ローマの信徒への手紙
尼寺へ行け
(オフィーリア、)私はおまえを愛してはいなかった。尼寺へ行け。
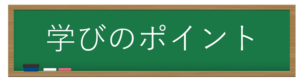
この場面は過去、様々に解釈されてきた。オフィーリアのことを愛していたハムレットが、なぜ突然オフィーリアに「尼寺へ行け」などと言うのか。
この「尼寺」は、文字通りに捉えれば「女子修道院」、当時の言葉遣いを踏まえると「売春宿」ということになる。
着目すべきは、この場面の直前にハムレットが「生きるべきか、死ぬべきか」すなわち「復讐すべきか、しないべきか」と悩み、「復讐する」と決意している点であろう。
復讐して自害することまで覚悟した人間が、愛する人に対して「売春婦になれ」などと言うだろうか。普通に考えれば「自分には君を幸せにできないが、せめて修道女になって、自分以外の男に触れず、純潔なままでいてほしい」という意味と捉えられるのではないだろうか(ハムレットの言い分はかなり身勝手ではあるが)。
しかし、解釈を非常に難しくしている要素の一つは、この場面をクローディアスとポローニアスが陰から見ているという事実である。ハムレットがそれに気付いていたならば、狂気を演出するために「売春婦になれ」と言い放っていてもおかしくはない。
ちなみにオフィーリアはその後、ハムレットに父(ポローニアス)を殺され、半狂乱に落ちったのち、小川で溺死してしまう。
理性と感情の間の揺れ動き
| 理性的 | 感情的 | バランス派 |
| ホレイシオ | レアティーズ | フォーティンブラス |
| ハムレットの友人 | ポローニアスの息子 | ノルウェー王子 |
| 常にハムレットを冷静な目で見守る | 父をハムレットに殺されたと分かるとすぐに挙兵 | 父をデンマーク王に殺されるが、名誉の為に復讐しない |
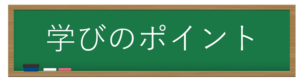
主人公ハムレットは、「気高くいきたい」という信念を持ちつつも、それをどう実現すべきかに悩み、理性と感情の間を行き来する。
理性的に考えれば、次のデンマーク王は自分なのだから、復讐などせずに今はじっと耐え忍べばいい。しかし、父と母と王座を奪ったクローディアスが感情としてどうしても許せず、復讐を企てる。それでもなお、本当に復讐が正しい手段なのかどうかを繰り返し考え続ける。
そんな心の動きを際立たせるように、ハムレットの周囲には「理性派」「感情派」「バランス派」の3名が配置されている。
まず友人のホレイシオは理性派と言える。常に冷静で、ハムレットが「この復讐劇の真相を語り継いでほしい」と依頼したのもホレイシオだった。宰相ポローニアスの息子でオフィーリアの兄であるレアティーズは感情派。王クローディアスにそそのかされるままに、ハムレットへの復讐を誓う。そして、結局最後にデンマーク王座に就くフォーティンブラスがバランス派である。
もともとが演劇作品であるため、各人の個性には若干極端な面もみられるが、それぞれキャラが「立って」いることも、この作品の魅力と言える。
人事部長のつぶやき
本作品随一の見どころ
【ハムレット】
今ならやれる。奴は祈っている。よし、やるぞ。〔剣を抜く〕 ──(しかし)やれば、奴は天国へ行く。それで復讐は成るのか。考えものだ。
悪党が父上を殺した、そのお礼に、一人息子の俺が、この悪党を送ってやるのか、天国に。それでは雇われ仕事だ。復讐ではない。
【王(クローディアス)】
言葉は宙に舞い、心は重く沈む。心の伴わぬ言葉は、天には届かぬ。
この場面では、ハムレットはクローディアスの背後を取っており、復讐の絶好の機会を得ている。しかし、クローディアスは祈っている。キリスト教の世界観では、神に祈りを捧げている最中に死ぬと、その人は天国に行くことになる。
クローディアスの死という実利が得られるにもかかわらず、ハムレットは復讐を思いとどまる。現代の感覚ではなかなか理解できないが、「絶対に地獄に落としてやる」という執念が感じられる。

本作品随一の名場面と言えるのではないでしょうか!
オフィーリアと夏目漱石
(オフィーリアの死の場面)
土手から斜めに柳が生え、小川の水面に白い葉が映るあたり。あの子はその枝で豪華な花飾りを作っていました。(中略)
その素敵な花輪を、垂れた枝にかけようと柳によじ登ったとたん、意地の悪い枝が折れ、花輪もろとも、まっさかさまに、涙の川に落ちました。裾が大きく広がって、人魚のように、しばらく体を浮かせて──そのあいだ、あの子は古い小唄を口ずさみ、自分の不幸がわからぬ様子── まるで水の中で暮らす妖精のように。
でも、それも長くは続かず、服が水を吸って重くなり、哀れ、あの子を美しい歌から、泥まみれの死の底へ引きずり下ろしたのです。
-300x246.jpg)

オフィーリア溺死の場面は多くの画家が題材としており、あの「民衆を導く自由の女神」を描いたドラクロワも取り上げている。しかし、最も有名なのは、19世紀イギリスの画家ジョン・エヴァレット・ミレーによって描かれた「オフィーリア」だろう。
ミレーはこの絵を描くためにモデルをバスタブに浮かべたが、冬だったのでモデルが風邪を引いてしまい、父親から損害賠償請求されたという逸話でも有名になっている。
夏目漱石はロンドン留学中にこの絵に感動したらしく、著書『草枕』の中で、オフィーリアについてこんな風に触れている。
ミレーのオフェリヤも、こう観察するとだいぶ美しくなる。何であんな不愉快な所を択(えら)んだものかと今まで不審に思っていたが、あれはやはり画になるのだ。
水に浮んだまま、あるいは水に沈んだまま、あるいは沈んだり浮んだりしたまま、ただそのままの姿で苦なしに流れる有様は美的に相違ない。それで両岸にいろいろな草花をあしらって、水の色と流れて行く人の顔の色と、衣服の色に、落ちついた調和をとったなら、きっと画になるに相違ない。

「草枕」では、主人公がミレーのような絵を描きたいが、自分らしさをどう出せばいいかに悩むというシナリオになっています。
(新潮文庫)
※福田恆存訳の新潮文庫版か、河合祥一郎訳の角川文庫版がおすすめ!
.png)

