スッタニパータ
(ブッダのことば)
基本情報
初版 1984年
出版社 岩波文庫など
難易度 ★★★☆☆
オススメ度★★★★★
ページ数 453ページ(但し注釈が多い)
所要時間 3時間00分
どんな本?
数ある仏教の経典の中では最古であり、釈迦の思想を最も正確に後世に伝えるとされる経典集。スッタは「経」、ニパータは「集まり」の意味。仏教思想の源泉を知るのに最適の一冊。
東洋における教養の教科書。後世への影響は計り知れない。どのような教養を身に付けるにせよ、東洋人である限り、本書と「論語」は必読の入門書。現在の仏教の教義は複雑だが、釈迦が語った仏教の神髄は非常にシンプルなので、すっと心に落ちてくる。
著者(釈迦)が伝えたいこと
あらゆる現象や物質は独立した実体を持たず、無限の関係性の中で絶えず変化する。財産・名誉・健康・愛する人との関係等々、確かなものなど一つもない。
自己を制御し、あらゆるものへの執着、すなわち煩悩を捨て、極端を避けて中道を生きる者は、その言葉・心・行為によって苦悩から離れ、永遠の輪廻地獄から脱し、不死・平安・不滅なるニルヴァーナ(涅槃)の境地に達することができる。
※釈迦は、現代の大乗仏教にみられる仏像崇拝や祈祷・念仏については一切語っておらず、ただ「自分自身と理法(=釈迦の教え)だけを頼りにせよ」と説いている

著者(釈迦の生涯と主な教え)
釈迦(紀元前5~7世紀)

名前は複数あるが、それぞれの由来は以下のとおり(本名については諸説あり)
釈迦:出身部族であるシャーキヤ族の名前から
ブッダ:「目覚めた者」という尊称
ゴータマ・シッダッタ :本名
・紀元前5〜6世紀頃、現在のインドとネパールの国境付近に生まれる。父は釈迦族の国王であるシュッドーダナ、母は隣国コーリヤの執政の娘マーヤー。
・誕生直後に四方に七歩歩み、右手で天を指し、左手で地を指して「天上天下唯我独尊(この世に生きる人々は私を含めて全て尊い)」と言ったとされる。
・宮殿から外に出る際、東の門に老人を、南の門に病人を、西の門に死人を見て絶望したが、北の門に老・病・死を克服しようとする修行者の姿を見て、自らも出家を決意する。
・6年もの苦行に耐え忍んでも悟りを得られず、衰弱しきっていた釈迦は、通りかかった村娘スジャータから乳粥を与えられて気力を回復する。
・また、スジャータの「琴の弦はきつすぎても緩すぎてもダメであり、適度に締めるのが望ましい」という歌を聴き、中道の尊さ及び苦行が間違いだったことを理解する。
・決意を新たにした釈迦は菩提樹の下で瞑想を行い、35歳で以下のような悟りの境地に至る。
【四諦(したい)】
釈尊が菩提樹の下で悟ったといわれる真理。
①苦諦(くたい):人生は苦である
②集諦(じったい):人間の煩悩が苦を生む
③滅諦(めったい):よって煩悩を断ち、悟りの境地(涅槃)に至るべきだ
④道諦(どうたい):そのためには「八正道」の実践が必要だ
【四苦八苦】
釈迦が定義した苦の源泉(前者4つが四苦、後者4つを足して八苦)。
①生
②老
③病
④死
⑤愛別離苦(あいべつりく):愛する人と別れる苦しみ
⑥怨憎会苦(おんぞうえく):嫌いな相手と会う苦しみ
⑦求不得苦(ぐふとくく):望むものが得られない苦しみ
⑧五蘊盛苦(ごうんじょうく):肉体や精神が思いどおりにならない苦しみ
【八正道(はっしょうどう)】
涅槃に至るための8つの実践項目。苦楽の極端を避け「中道」を生きよという教え。
①正見(しょうけん):正しい世界観(正しい四諦の理解)
②正思(しょうし):正しい思惟
③正語(しょうご):正しい言葉遣い
④正業(しょうごう):正しい行い
⑤正命(しょうみょう):正しい生活
⑥正精進(しょうしょうじん):正しい努力
⑦正念(しょうねん):正しい信念(貪りや憂いをなくす)
⑧正定(しょうじょう):正しい精神統一
【三法印(さんぼういん)】
「生きるとは何か」という問いに対する釈迦の最終結論。
①諸行無常:世の中のすべての現象は常に変化し生滅して、永久不変なものはない
②諸法無我:世の中のすべての現象には主体などない
③涅槃寂静:煩悩を全て消し去ると、穏やかな世界が待っている
※一切皆苦:この世は苦しいことばかり、を加えて四法印とすることもある
こんな人にオススメ
仏教に関して一定の基礎知識があり、更に理解を深めたい人。少し人生に疲れてきた人。心静かに人生を送りたい人。
書評
仏典というと小難しいイメージがあるが、本書では中道の大切さや苦しみからの離脱、輪廻転生、「空」の考え方など、仏教の神髄とも言える教えが極めてシンプルに表現されている。釈迦自身が語った内容がそのまま記されているので、非常に読みやすい。
ただし、大切な教えは言葉を変えて何度も登場するので、若干の冗長感は否めない。また、同じ釈迦の言葉でも相互に矛盾するような教えも登場するので、読んでいて混乱することもある(仏教の世界では「語る相手や状況によって釈迦の表現が変わるのは当然」と捉えられているようだ)。
なお、注釈も多いので、本気で全てを理解しようと思うと骨が折れる。学術研究ではなく、教養の一環として読むのであれば、細部にはこだわらずに、教えの要点だけを理解できれば十分だろう。
(岩波文庫)
※仏教最古の古典だが、宗教というより道徳論や修身論の趣き
要約・あらすじ
第一 蛇の章(1~221)
■あらゆる欲望や感情を制御し、世の中に確固たるものなど無いことを悟り、極端に走ることなく中庸を旨とする者は、その言葉・心・行為によってこの世への執着を捨て去り、苦悩から離れ、永遠の輪廻地獄を脱し、不死・平安・不滅なるニルヴァーナ(涅槃)の境地に達する。
■賢者は独立自由であれ。あらゆる欲望、生と死、悪友、家族、財産、哲学的論争から自由であれ。家族や朋友に情が移ると執着が生まれ、それが苦しみを生む。妻を持つ在家者より、妻を持たない修行者の方が涅槃に近いのはこの理由による。独り居ることが聖者の道だ。ただし、自分と同じか優れた朋友とは積極的に交際せよ。
■悪魔は言う「人は家族や財産に執着があるから、家族や財産について喜ぶ。執着のない者の人生には喜びがない」。しかしそうではない。人は家族や財産について憂うから、人生が苦しいのだ。執着が無くなれば、人生は苦しくなくなる。
■親が子を大切に思うのと同様に、人間は生きとし生ける全てのものに、慈しみの心、すなわち楽しみを与え、苦しみを除く精神を持たなければならない。彼らと私は同じであると考え、殺生をしてはならない。
■次のような者は破滅する。①理法を嫌う(無知)②悪い人と付き合う③怠け者・怒りっぽい④親孝行しない⑤嘘・陰口を言う⑥自分だけが贅沢する⑦血筋と財産を誇り驕る⑧酒・女・賭博に耽る⑨不倫⑩老いてからの女遊び⑪浪費⑫権利欲⑬殺生⑭怠惰。
第二 小なる章(222~404)
■幸せとは次のようなことを言う。
①賢者と交わる
②目標を持つ
③学問と技術を身に付ける
④家族と仕事を大切にする
⑤理法(釈迦の教え)
⑥謙虚さと感謝
⑦やさしい言葉遣い
⑧煩悩や生死を超えた涅槃
■理法(釈迦の教え)に反し、煩悩に屈する者は、地獄に行き、永遠に輪廻の暗黒から抜け出すことができない。
■昔のバラモンたちは、戒律を守り、殺生もせず、苦行に励んでいたが、次第に蓄財や女性等への欲に溺れ、今ではすっかり堕落してしまった。指導者層の堕落により、クシャトリア、ヴァイシャ、シュードラも互いに分裂して仲違いしている。
■修行者の心得は次のとおりである。①定められたときにのみ托鉢する②物体・音・味・匂い・触れられるものへの欲望を抑える③内省する④真理を語る⑤批判に反発しない⑥善い言葉を遣う。
■これらは在家信者(所有の煩いがある人)には難しいだろうから、在家信者は少なくとも次を守るべきだ。①殺生しない②盗まない③姦淫しない④嘘をつかない⑤飲酒しない。
第三 大いなる章(405~765)
■出家後、悟りを開くまでの修行の期間、釈迦は悪魔から「苦行をやめよ」「ヴェーダの祭祀を行い、功徳を積め」という誘惑を受けるが、バラモン教を否定していた釈迦はその誘惑を退けた。
■人間には欲望や執着があるが、人間はいずれ亡くなる。しかし人間には理性がある。理性に頼って執着から脱すれば、憂いや苦しみは無くなるのだ。
■輪廻転生することは、迷える生を繰り返す無益な苦である。この輪廻の苦をありのままに知り、生に対する執着を超越し、結果的に輪廻から脱する人をブッダと呼ぶ。
■血統と育ちのどちらが重要かと問われれば、明確に「育ち」である。人間は自然界の中で同一の種であって、生まれによる身体的特徴に差異はない。人種・階級・職業は人それぞれだが、それらは単に名称が異なるだけである。ただし、行為によって人は卑しくもなり、尊くもなる。
■次のような行為をする人をバラモンと呼ぶ。人はバラモンに生まれるのではなく、バラモンになるのである。①執着がなく無欲②忍耐・冷静③謙虚④聡明⑤独立⑥不殺生⑦穏やか⑧正しい言葉。
■逆に、嘘をついたり、悪口を言ったり、快楽に溺れたりするものは地獄に落ちる。地獄では鉄の串に突き刺され、灼熱の鉄球を食わされ、炭火の上に臥せられ、血や蛆虫で満たされた釜で煮られ、剣の林で手足を切断され、剃刀の川で傷つけられ、犬やカラスに啄まれる。しかもほぼ永遠に。
■生老病死の苦しみには、無知や執着の他にも、ある事柄を「苦しい」と感じてしまう認識など、様々な原因がある。しかし、逆に言えば、それらの原因を全て無くしてしまえば、苦しみも消滅することになる。
第四 八つの詩句の章(766~975)
■人間を突き動かしているものは欲望である。欲したものが手に入れば喜び、そうでないなら悩み苦しむ。欲望が執着を生み、執着が苦しみを生む。
■人々は「自分こそが真理」と他を批判するが、世の中に一つしかない真理を語るのであれば、言い争う必要はない。真の賢者は、他人に簡単に同調することも、自説に固執することもない。私(釈迦)は自説が偏見であることを理解し、一切の哲学的断定を捨てているから、他の賢者と形而上学的な論争をしないのだ。
■修行者は心のうちが平安・平静であるべきで、自分の外側に静穏を求めてはならない。過去に拘らず、今くよくよせず、未来を憂わない。よく思慮し、焦らず、イライラしない。貪らず、妬まず、傲慢にならず、陰口を叩かない。自分を他人と比べて「優れている」とか「劣っている」などと言わない。そのような戒律を守ることが必要だ。
第五 彼岸に至る道の章(976~1149)
■世界は「空」であると考えよ。「空」とは、あらゆる現象や物質は独立した実体を持たず、無限の関係性の中で絶えず変化するという世界観のことである。
■世界は「空」なのだから、「○○は私のもの」という我執は捨てるべきだ。人間は家族や財産を愛し、執着するが、それは「家族や財産は我に属する」という考えがあるからだ。しかし、自分で制御できず、時とともに移ろいゆくものを、どうして頼りにできよう。「なぜ自分の思い通りにならないのか」と苦しみを生む一方ではないか。
■自己の身体も「我に属する」と考えてはいけない。自己の身体も含めてあらゆるものに対する愛欲、執着、貪欲などを断じ、それらを超越して始めて彼岸、すなわちニルヴァーナ(涅槃)の境地に達することができる。
学びのポイント
「中道」こそが悟りに繋がる
彼は両極端を知りつくして、よく考えて、両極端にも中間にも汚されない。彼をわたくしは「偉大な人」と呼ぶ。(本書より)
修行僧らよ。出家者が実践してはならない二つの極端がある。
一つはもろもろの欲望において欲楽に耽ることであって、下劣・野卑で凡愚の行いであり、高尚ならず、ためにならぬものである。
他の一つはみずから苦しめることであって、苦しみであり、高尚ならず、ためにならぬものである。真理の体現者はこの両極端に近づかないで、中道をさとったのである。
修行僧らよ、真理の体現者のさとった中道とは──それはじつに〈聖なる八支よりなる道〉である。すなわち、正しい世界観、正しい思惟、正しい言葉遣い、正しい行い、正しい生活、正しい努力、正しい気遣い、正しい精神統一である。(仏教初期の経典「サンユッタ・ニカーヤ」より)

これらは端的に「物事の本質は両極端の間のどこかににある」という中道・中庸の道を説いている。

あくまで「両極端の間のどこか」であって、足して2で割った「中間」とは言っていないことに注意しましょう!
釈迦は「生・老・病・死」という苦から逃れるために、断食の苦行や呼吸を止める苦行など、体が骨と皮だけの姿になるまで苦行に励んだが、苦しみを解決することはできなかった。
その際、釈迦に乳粥を与えてくれたスジャータが「琴の弦はきつすぎても緩すぎてもダメであり、適度に締めるのが望ましい」と歌ったのを聴き、一方の極端である苦行が間違いだったことを理解する。
その後、釈迦は菩提樹の下で回想し、恵まれすぎていた王宮での生活もまた一方の極端であり、極端を避けて「八正道」という中道を生きることが、涅槃(心が平穏でいられる悟りの境地)に至るために必要だという真理に至る。(八正道については前述のとおり)
通常の仏教解説であればここまでだが、さらに面白いのは、紀元前の3大思想と言われている「仏教」「儒教」「ギリシャ哲学」が揃いも揃ってこの「中道・中庸」を説いていることである。

徳を考える上で大切な概念は「中庸」である。例えば節制であれば、両極端である「臆病」と「向こう見ず」の間のどこかに、適切な節制の水準というものが存在する。
アリストテレス『二コマコス倫理学』

物事は極端すぎてはいけない。道徳において「中庸」であることは大切である。
孔子『論語』
当時、直接的な交流は無かったであろうヨーロッパ・インド・中国で同時に説かれ、それが現代にまで脈々と受け継がれているということは、この「中道・中庸」という考え方は、人類にとって普遍的であると言ってよいのではなかろうか。
なお、「サンユッタ・ニカーヤ」では、この中道主義が「空」の考え方に基づいて分かりやすく解説されている。
カッチャーヤナよ、この世間の人々は多くは二つの立場に依拠している。それは、すなわち有と無とである。
もしも人が正しい知慧をもって世の人々の現れ出ることを如実に観じるならば、世間において無はありえない。また人が正しい知慧をもって世間の消滅を如実に観じるならば、世間において有はありえない。
カッチャーヤナよ、「あらゆるものがある」というならば、これはひとつの両極端である。「あらゆるものがない」というならば、これも第二の両極端である。人格を完成した人は、この両極端説に近づかないで、中〔道〕によって法を説くのである。
涅槃=苦しみがない>喜びがある
悪魔は釈迦にこう囁いた。「人は子(家族)や牛(財産)に執着し、喜びを感じる。執着するものが無ければ、喜びもない」
一方、釈迦はこう否定した。「人は子(家族)や牛(財産)に執着し、憂いや苦しみを感じる。執着は憂いや苦しみを生むのだ。執着するものが無ければ、どちらも無くなるのである。」

釈迦は、人生において「喜びを追い求める」ことより「苦しみを無くす」ことを優先するように説いている。
非常に興味深いのは、先ほどの「中道」と同じく、アリストテレスも全く同じことを説いていることだ。
思慮深い人は、快楽を追求せずに、苦痛のないことを追求する。(中略)
苦痛がないとは、人生を妨げるものが無いということを意味し、それは最高善の一つであるからだ。
アリストテレス『二コマコス倫理学』
そしてこの考え方は、後世にも影響を与え続けている。例えば、江戸時代の思想家である佐藤一斎は、西郷隆盛が座右の書としたことで有名な『言志四録』の中で、こう言っている。
わざわざ幸せを求める必要はない。災いさえなければ幸せだ(言志耋録154)
また、19世紀ドイツの哲学者ショーペンハウアーは、著書『幸福について』でこう述べている。
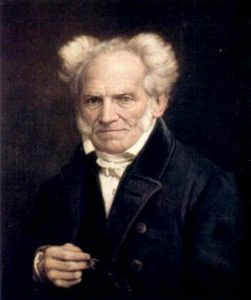
私はあらゆる生きる知恵の最高原則は、アリストテレスが『ニコマコス倫理学』でさりげなく表明した文言「賢者は快楽を求めず、苦痛なきを求める」だと考える。
幸福論は、幸福論という名称そのものがいわば粉飾した表現であり、「幸せな人生」とは、「あまり不幸せではない人生」、すなわち「まずまずの人生」であると解すべきだという教えから始めねばならない。
ショーペンハウアー『幸福について』
こちらも「中道・中庸」と同じく、洋の東西で全く同じことが説かれ、そして2000年以上経った現代にまで語り継がれているという点において、人類にとって普遍的な考え方と言えるだろう。
【参考】自分を愛し、他者をも愛する
・どの方向に心で探し求めてみても、自分よりもさらに愛しいものをどこにも見出さなかった。そのように、他の人々にとっても、それぞれの自己が愛しいのである。それ故に、自己を愛する人は、他人を害してはならない。(サンユッタ・ニカーヤ(ブッダ 神々との対話)より)
・先ず自分を正しくととのえ、次いで他人を教えよ。(ダンマパダ(法句経)より)

先ほども出てきた初期仏教の経典である「サンユッタ・ニカーヤ」では、自己愛について語られている。こちらも西洋思想と共通しているので、参考として挙げておきたい。
やや意外かもしれないが、仏教においては「自己愛」が積極的に肯定されている。そして「他人においても自分が一番なのだから、自分を愛する人は他人も大切にしなければならない」としている。
そしてこれも、「中道」や「苦しみが無い>喜び」と同じく、アリストテレスが著書『ニコマコス倫理学』で全く同じことを言っている。
自分すら愛せない者に、他人を愛することはできない。善き人は自分自身の存在が善であるから、自分自身を愛している。そして、自分に対するように友人にも対する。だから友人も愛せるのである。
(趣旨要約)
そしてこの考え方は、キリスト教の「隣人愛」に引き継がれ、ヨーロッパでは主流の考え方となっていく。ドイツの精神分析学者エーリッヒ・フロムは、著書『愛するということ』で以下のように述べている。

聖書に表現されている「汝のごとく汝の隣人を愛せ」という考え方の裏にあるのは、自分自身の個性を尊重し、自分自身を愛し、理解することは、他人を尊重し、愛し、理解することとは切り離せないという考えである。
自分自身を愛することと他人を愛することとは、不可分の関係にあるのだ。
また、ロシアの文豪トルストイは著書『人生論』でこのように述べている。
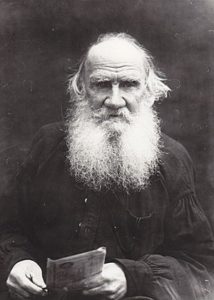
人は自分のために生きるべきだろうか?だが、自分の個人的な生命は悪であり、無意味ではないのか。家族のために生きるべきだろうか? 共同体のためにか?いっそ祖国か、人類のためにか?
しかし、自分個人の生命が不幸で無意味だとすれば、あらゆる他の人間個人の生命も同じように無意味なわけだから、そんな無意味で不合理な個人を数限りなく寄せ集めてみたところで、一つの幸福な理性的な生命をも作ることになるまい。
日本の哲学者三木清も、「個人の幸福」より「国の戦争勝利」を優先した戦時下の日本において、「自分が幸福であることが、他者にとっても最善である」と説いた。

幸福は徳に反するものでなく、むしろ幸福そのものが徳である。もちろん、他人の幸福について考えねばならぬというのは正しい。しかし我々は我々の愛する者に対して、自分が幸福であることよりなお以上の善いことを為し得るであろうか。
自己を制御する
悟りを得た者は自己を制している。彼は他人に悩まされることなく、また何人をも悩まさない。諸々の賢者は、かれを聖者であると知る。

これはそのまま、古代ギリシャを起源とするストア派哲学が主張する「自らが制御できるもののみを制御し、それ以外は気にしてはならない」という教えと重なる。
【ストア哲学の基本的な考え方】
・人間は幸福に生きることを目的にしなくてはいけない。
・財産や地位といったものは人為的で生きる目的にならない。宇宙や自然を支配する秩序や法則に従って生きることこそが、人生の目的となり得る。
・幸福とは、この宇宙を支配する秩序に従い、理性(ロゴス)によって感情(パトス)を制して、不動心(アパティア)に達することである。
・不動心に至るには、我々にはコントロールできるものとできないものがあることを自覚し、コントロールできるものに注力し、コントロールできないものに囚われないという態度が必要である。
アパティアとは「a-patheia(パトスの無いこと)」を意味し、パトス、すなわち情念や欲情に支配されない、超然とした境地のことを指す。これは、煩悩の無い悟りの境地である涅槃と同様の意味と考えられる。
仏教の源流であるバラモン教の創始者であるアーリア民族が「インド・ヨーロッパ語族」に属することを考えると、仏教とギリシャ哲学に共通点があってもおかしくない。しかし、人的交流が少なかった紀元前後において、異なる地域で全く同じような考え方が複数広がっていたという事実は、注目に値するだろう。
なお、初期仏教の経典「ダンマパダ」では、自己制御について分かりやすくこう説明している。
この心は、以前には、望むがままに、欲するがままに、快きがままに、さすらっていた。今やわたくしはその心をすっかり抑御しよう──象使いが鉤をもって、発情期に狂う象を全く押さえ付けるように。
「慈悲」の心の大切さ
一方、仏教はヨーロッパ思想には見られない、独自の思想も展開する。少し長いが、今でもスリランカ、ミャンマー、タイ等で独立した経典として読誦される「慈しみの経」を引用する。
他の識者の非難を受けるような下劣な行いを、決して為してはならない。一切の生きとし生けるものは、幸福であれ、安穏であれ、安楽であれ。
いかなる生物生類であっても、怯えているものでも強剛なものでも、悉く、長いものでも、大きなものでも、中くらいのものでも、短いものでも、微細なものでも、粗大なものでも、目に見えるものでも、見えないものでも、遠くに住むものでも、近くに住むものでも、すでに生まれたものでも、これから生まれようと欲するものでも、一切の生きとし生けるものは、幸せであれ。
何ぴとも他人を欺いてはならない。たといどこにあっても他人を軽んじてはならない。悩まそうとして怒りの想いをいだいて互いに他人に苦痛を与えることを望んではならない。
あたかも、母が独り子を命を賭けても護るように、そのように一切の生きとし生けるものどもに対しても、無量の慈しみのこころを起すべし。
また全世界に対して無量の慈しみの意を起すべし。上に、下に、また横に、障害なく怨みなく敵意なき慈しみを行うべし。立ちつつも、歩みつつも、坐しつつも、臥しつつも、眠らないでいる限りは、この慈しみの心づかいをしっかりと保て。この世では、この状態を崇高な境地と呼ぶ。

一見するとキリスト教の「隣人愛」のようにも見えるが、とにかく一貫して「無私無欲」を説いている。これは「キリスト教の布教のため」という名目で、アメリカ大陸やアジアにおいて略奪の限りを尽くしたヨーロッパ諸国の鼻息の粗さとは正反対の慎ましさを示している。
人間は神が創った最上位の存在と信じ、自然を支配し、自然を支配する法則を明らかにすることが使命と考えて科学技術を発達させてきたヨーロッパ人と、慎ましく足るを知り、心を平静に保ち、全ての生き物を大切に生きることを優先してきた仏教圏の人々。
グローバル化、すなわち全世界の欧米化が進行し始めて久しいが、その波に飲み込まれず、仏教圏的な生き方をする権利が保障されても良いのではないだろうか。
「空」という考え方
常によく気をつけ、自我に固執する見解をうち破って、世界を「空なり」と観ぜよ。そうすれば死を乗り超えることができるであろう。

「空」といえば、般若心経の「色即是空 空即是色」でご存知の方も多いのではないだろうか。
この「空」という思想は、長らく大乗仏教になってから出てきた教えであって、初期の原始仏教にはなかったと考えられてきたが、既に原始仏教の時代から存在した。
「空」とは「あらゆる現象や物質は独立した実体を持たず、無限の関係性の中で絶えず変化するという世界観、あるいは世界全体」を指す。そして「色」は「人間が認識できる現象や事物のこと」を表す。
よって、「色即是空 空即是色」は「あらゆるものは無限の関係性の中で絶えず変化しているのだから、「色」など無い。そして同時に、人間は「空」の一部を「色」として捉えているので、「色」はあるとも言える」という意味になる。
悪魔の誘惑=バラモン教からの攻撃
ネーランジャラー河の畔で瞑想していた私に、悪魔はいたわりの言葉を発しつつ近づいてきた。
「あなたはやせ細り、もう死んでしまいそうではないですか。苦行などやめて、生きなさい。ヴェーダの祭祀を行い、多くの功徳を積みなさい」
しかし私は言い返してやった。「悪しき者よ、汝は現実世界の功徳を求めてここに来たのだが、私には不要である。私は無欲に生きるための悟りを得ようとしているのだ」
(趣旨要約)

ここで言う「悪魔」とは、釈迦がバラモン教から受けた攻撃のことを指しているとされる。
バラモン教では世俗的な祭祀を尊重したのに対し、ブッダはそれらを「堕落している」と否定し、人間の内面的・精神的な面に心を向けた。だからこそ、悪魔からの「誘惑」に打ち勝つことができた、というエピソードになっている。
当時のインド北部では商工業や貨幣経済が発達し、商工業者が経済の実権を握るようになって、バラモンが全てを牛耳るバラモン教に対抗して様々な思想が生まれており、仏教もその一つとして非バラモン層に急速に受け入れられていったという時代背景と合わせると、理解しやすいだろう。
仏教はバラモン教へのアンチテーゼ①
昔のバラモンたちは自己を慎む苦行者であった。かれらは五種の欲望の対象を捨てて、自己の理想を行なった。バラモンたちには家畜も黄金も穀物もなかったが、ヴェーダの読誦を財宝とし、穀物とし、ブラフマンを倉として守っていた。(しかし、今は堕落してしまっている)。
現世を望まず、来世をも望まず、欲求もなくて、とらわれのない人、彼を私はバラモンと呼ぶ。
※五種の欲望の対象=人間の5種の感覚器官(目・耳・口・鼻・触)で捉えられる対象
※ヴェーダ=バラモン教の聖典
※ブラフマン=宇宙の根源、宇宙を支配する真理

インドでは紀元前5000年頃に「インダス文明」が栄えたが、紀元前1500年頃にはアーリア人が中央アジアのステップ地帯からインド北部のパンジャブ地方に侵入した。その後も先住民のトラヴィダ人やムンダ人を圧迫しながら南下を進め、ついにインド全体の支配層として君臨するようになる。
アーリア文化の社会では、支配体制を保持するために、大きくは四つの階級であるバラモン(司祭)、クシャトリヤ(王族)、ヴァイシャ(庶民)、シュードラ(隷民)に分け、先住民はシュードラかそれ以下の身分にされた。
中でもバラモンは、社会の戒律・道徳・哲学等を専有して王族の上位に位置されていたが、その特権的地位に甘んじて祭祀の対価を求めるなど、だんだんと堕落していく。
バラモン教の教え、その中でも「ウパニシャッド哲学」と呼ばれている教義にある「輪廻転生」や「解脱」という考え方は仏教にもそのまま引き継がれているが、釈迦はバラモンの堕落を厳しく批判し、「欲を捨て、徳を備えなければならない」として新しい教えを確立することになる。
すなわち、仏教はバラモン教へのアンチテーゼとして生まれたものとも言える。
仏教はバラモン教へのアンチテーゼ②
・生れを問うことなかれ。行いを問え。火は実にあらゆる薪から生ずる。賤しい家に生まれた人でも、聖者として道心堅固であり、恥を知って慎しむならば、高貴の人となる。
・人はバラモンに生まれるのではなく、(行為によって)バラモンになるのである。人は賤しく生れるのではなく、(行為によって)賤しい人になるのである。

仏教が「平等」を説いたのも、厳しい世襲の身分制度を維持したバラモン教へのアンチテーゼと言える。この教えにより、仏教はバラモン教に反発する新興勢力からの支持を得ていくことになる。
釈迦が亡くなってから数百年後の紀元前3世紀には、マウリヤ朝が南端部分を除くインド亜大陸全土を統一。第3代アショーカ王は仏教の教えに基づき政治を行い、その教えを刻んだ石碑をインド各地に作って仏教を手厚く保護した。
一方、バラモン教も危機感を募らせ、祭祀と儀礼だけにこだわらず、土着の神々への信仰を取り入れることで、自らをヒンズー教へと変化させて仏教徒をヒンズー教徒に取り込んでいった。
仏教は仏教で、個人の修行や悟りを重視した小難しい上座部仏教から、「自分だけでなくあらゆる人を救う」とする大乗仏教が分離し、「現世利益のために祈る」という(釈迦の教えにはない)ヒンズー教の形式を取り入れることまでして世俗化して支持を広げようとするが、シンプルさではヒンズー教に叶わず、インド以外の国で生き延びるようになる。
大乗仏教は7世紀に日本にまで広がることになるが、例えば如来・菩薩・明王のほか、毘沙門天・帝釈天・梵天等の偶像崇拝や、現世利益のための祈祷や念仏といった要素は、初期仏教には一切見られないという点は特筆に値する。仏教は釈迦の時代に比べてかなり世俗化したと言えるだろう。
また、身分制度を否定して平等を説いた仏教がインドから追いやられ、身分制度を前提とするバラモン教・ヒンズー教が今日までインドで根付いているというのは、非常に不思議であるとも言える。
なお、インド国内で力を失った仏教ではあるが、近年では見直しの動きも出てきている。1950年代後半には、独立インドの初代法務大臣であるアンベードカルが、カースト最下層のために新仏教運動を展開し、50万人もの人が仏教に改宗した。
また、独立インドの国旗の中央には「法輪(ダルマ・チャクラ)」が描かれている。「法」は釈迦が説く教え、「輪」は古代インドの武器を意味し、「法輪」で「仏の説く正法が邪見を破り悪をくじいて、世に広く伝わるさま」を表している。
インド国旗に描かれている法輪は、前述のアショーカ王が立てた石碑に多く刻まれていたことから「アショーカ・チャクラ」と呼ばれ、釈迦が菩提樹の下で悟ったとされる「十二縁起」を表している(ちなみに上部のサフラン色はヒンズー教、下部の緑はイスラム教を表す)。

【参考:十二縁起(じゅうにえんぎ)】
老いや死という苦しみは、遡れば人間の無知に起因するので、無知が無くなれば、老いや死という苦しみもなくなるとする。アショーカ・チャクラには24本のスポークがあり、最初の12本は「①があるから⑫がある」という動き、後ろの12本は「①がなくなれば⑫もなくなる」ことを表している。
①無明(無知)→②行(能動性)→③識(識別)→④名色(名前と現象)→⑤六処(感受)→⑥触(接触)→⑦受(受容)→⑧愛(欲望)→ ⑨取 (執着)→⑩有(生存)→⑪生(誕生)→⑫老死(老いと死)
<参考:バラモン教・仏教・ヒンズー教>
①バラモン教(紀元前12世紀頃)
(成立)アーリア人が先住のトラヴィダ族を支配する過程で成立。バラモン階級が独占する自然多神教で、アーリア人=支配階級、先住民=被支配階級というカースト制度の源流にもなった。
(教義)神が宇宙を創造したとする多神教。輪廻転生を繰り返すばかりだと苦しみから逃れられないので、そこから離脱(=解脱)することを目的とする。
②仏教(紀元前5世紀)
(成立)「バラモン教は堕落している」として、バラモン教の神・祭祀・身分制度を否定し、自己の解放を目指した新しい宗教。身分制度を否定したため、新興資産家等からも支持された。
(教義)輪廻の考え方はバラモン教から継承し、苦しみから解放される「悟り」に達することを目的とする。教義は複雑だが普遍性があるため、世界宗教と位置付けられる。
③ヒンズー教(紀元前4世紀~紀元後4世紀)
(成立)バラモン教が土着の民間信仰を取り込んで民族宗教として成立。
(教義)仏教同様に輪廻の考え方はバラモン教から継承しているが、特定の経典は持たず、教義は多彩。バラモン教とヒンズー教は本来同一宗教だが、インド土着の民間信仰を取り込む前のものを特に「バラモン教」と呼んでいる。
人事部長のつぶやき
常に内面に向かう仏教
修行者は心のうちが平安となれ。外に静穏を求めてはならない。内的に平安となった人には取り上げられるものは存在しない。どうして捨てられるものがあろうか。
形式的な祭礼主義や戒律主義に陥っていたバラモン教とは逆に、釈迦は各個人が煩悩を捨て去り、涅槃に到達するという内面の努力を重視した。
この手の「原点回帰」はいつの時代にも見られ、例えば宗教改革を始めたマルチン・ルターも、その言い分は「信仰によってのみ、人は救われる」というものだった。
この「結局、心の平安、すなわち心の幸福は自分自身の中にしかない」という考え方は、もちろん人によって好き嫌いはあるだろうが、私は「まさしくそうだよなあ」と考えるタイプである。
先ほど出てきたドイツの哲学者ショーペンハウアーはもう一歩進んでいて、著書『幸福について』では、以下のとおり「自分の外側に平静や刺激を求めるのは凡人」とバッサリぶった切っている。
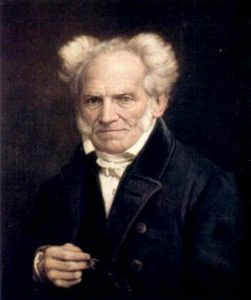
そもそも人間は、自分自身を相手にしたときだけ、「完璧な調和」に達することができる。友人とも恋人とも「完璧な調和」に達することはできない。個性や気分の相違は、たとえわずかではあっても、必ずや不調和を招くからだ。
だから、心の真の深い平和と完全な心の安らぎという、健康に次いで最も貴重な地上の財宝は、孤独のなかにしかなく、徹底した隠棲のうちにしか見出すことができない。偉大で豊かな自我の持ち主は、そうした場合、このみじめな地上で見出しうる、もっとも幸福な状態を享受するだろう。
価値と豊かさを内面に備えた人は、他人との連帯を得るために多大な犠牲を払ったりはしない。それは自分ひとりで満ち足りた心境にあるからだ。
凡人は、これと反対の気持ちから社交的になり、調子を合わせる。凡人は、自分自身に耐えるよりも他人に耐えるほうが楽だからである。
自己の内面の空虚さから逃れるために、人は社交する
賢者は内面に備わっているものが大きく、外部刺激を必要としないが、愚者は内面が空虚なため、それを気晴らしや社交で埋めなければならない。
人生は苦しみだけではない
世界は美しいものであり、人間の生命は甘美なものだ。
これは本書からの引用ではなく、釈迦の最期を記した「マハーパリニッバーナ・スッタンタ」という経典からの引用です。
仏教は基本的に「人生は苦しいから、そこから抜け出そう」という、ある意味「マイナススタート」の世界観を持っています。
しかし、自分を制御し、あらゆる煩悩から抜け出しニルヴァーナに達するとき、ついに「人生の味わいの深さ、美しさ、楽しさ、喜び」を体得し、「世界は美しく、人生は甘美である」と世界観が180度変わるのです。

後の仏教が生み出した「極楽浄土」のイメージに近いかもしれませんね
悲しみはすぐにかき消す
例えば家に火がついているのを水で消し止めるように、立派な人は、悲しみが起ったのを速かに滅ぼしてしまいなさい。
「自己の感情を制御し、苦しみを超越して涅槃に至れ」という教えが分かりやすい例え話で説かれています。
悲しみを悲しみと思うから、人は苦しむわけです。古代ギリシャの哲学者エピクテトスは「事態が人間を不安にするのではなく、事態に対する見解が人間を不安にする」と述べましたが、世界や事象の捉え方によって、人は苦しむこともできますし、それを乗り越えて涅槃に至ることもできます。
すべては自分次第である、という初期仏教のストイックな点は、後世の「念仏さえ唱えれば極楽に行ける」といった大衆迎合型仏教とは明確に一線を画していると言えるでしょう。
地獄は最初から存在した
嘘をついたり、悪口を言ったり、快楽に溺れたりするものは地獄に落ちる。
地獄では鉄の串に突き刺され、灼熱の鉄球を食わされ、炭火の上に臥せられ、血や蛆虫で満たされた釜で煮られ、剣の林で手足を切断され、剃刀の川で傷つけられ、犬やカラスに啄まれる。しかもほぼ永遠に。
(趣旨要約)
古代インドでは、生前に罪を犯したものは「ナラカ」という地下の牢獄に落ちて罪を償うとされていました。これが初期仏教では地獄として取り入れられることになります。
地獄の姿は上で引用したとおりかなりエグいのですが、地獄にもさまざまな種類があり(アッブダ地獄、ニラッブダ地獄、アババ地獄、アハハ地獄、アタタ地獄等)、その名称がなかなか個性的です。アハハ地獄なんて、「くすぐりの刑」が執行されていそうですね。
なお、日本人が地獄というと閻魔大王を連想しますが、閻魔は古代インドにおける死者の世界の王「ヤマ」の音訳で、のちに仏教に取り入れられています。

ちなみにサンスクリット語のナラカは奈落の語源で、現在でも「奈落の底に落ちる」などと使われています!
(岩波文庫)
※仏教最古の古典だが、宗教というより道徳論や修身論の趣き
.png)

