「こころ」夏目漱石
基本情報
初版 1914年
出版社 角川文庫、新潮文庫等
難易度 ★★★☆☆
オススメ度★★★★★
ページ数 335ページ
所要時間 4時間00分
どんな本?
明治の文豪、夏目漱石後期の作品。私が慕う「先生」が、一人の女性を巡って親友Kを裏切った過去を悔んで、自も命を絶つ物語。近代人の孤独や生きにくさを描き出す。
日本における文庫本の発行部数では歴代第1位で、日本の小説ジャンルの最高峰。
著者が伝えたいこと
儒教、封建制、武士道といった高い道徳・倫理観・自制心を尊ぶ「前近代的な精神」は、既に時代遅れとなってしまった。
急激な欧米化、即ち自由・独立・個人主義の台頭により、今後は日本でも個人の自由意思を尊重する時代になっていくだろう。しかし、その代償として、日本人は何らかの孤独に苛まれるはずである。
(自分自身の欲望に個人主義的に素直に従ったのが「私」、私を責めることなく武士道的に潔く死を選んだのがKということになる)。

著者
夏目漱石 1867-1916

日本の英文学者・小説家。本名は夏目金之助。近代日本文学における文豪の一人。1984年から2007年まで発行されていた千円札の肖像でもあった。
1893年東京帝国大学英文科を卒業後、1895年松山中学教諭、1897年旧制第五高等学校(熊本)教授を経て、1900年にイギリスに留学。帰国後、東京帝大等で英文学を講義。1905年に「吾輩は猫である」により作家としてデビューした。その後、創作活動に専念するため、1907年に朝日新聞に入社する。
代表作に「坊っちゃん」「草枕」「虞美人草」「三四郎」「それから」「門」「明暗」そして本書「こゝろ」などがある。1916年、50歳で亡くなる。
高名な人物ではあるが、人生自体は不遇が多く、作品では「孤独」や「生きにくさ」といった感情が扱われることが多い。若い頃に患った肺結核、英国留学時の神経衰弱、東京帝大での教師としての不評(小泉八雲の後任だった)、そしてその後の胃潰瘍等を経て、本作品は夏目の晩年に書かれている。
こんな人にオススメ
有名な文学作品に触れてみたい人、高校生の現代文の授業で印象に残っている人、友情・裏切り・呵責・孤独・生きにくさ等のテーマに関心のある人
書評
新聞に連載されていたため、一つ一つの章が短く、テンポよく読める。登場人物の心理描写や、処世訓に関する比喩表現など、さすが文豪と呼ばれるだけはあると納得させられる作品。
全3部からなるが、中心は第3部の「先生と遺書」。高校の教科書で取り上げられるのも第3部の後半部分。一般的には良心の呵責に耐えきれなくなった「先生」の自殺が主題とされるが、自制的で素直で真面目なKの自殺を「前近代的人間の終焉」とする副題も読みどころ。
\本書は30日間、無料で読めます!/
\専用端末無しで読めます!/

要約・あらすじ

第1部 先生と私
■当時学生だった私は、鎌倉で「先生」と知り合う。先生は人を寄せ付けない雰囲気を持っていた。自分を「(交友の少ない)寂しい人間」と称し、自らの懐に入ろうとする者を、手を広げて抱きしめることが出来ないような人だった。
■しかし、私はそんな先生に言葉に出来ない魅力を感じ、東京に帰ってからも先生の家をしばしば訪ねるようになった。
■先生は大学卒で博識だったが仕事はしておらず、世俗の世界から逃れていた。人を信用しないその厭世的な様子は、先生の父親が亡くなった際に遺産相続で親族に裏切られたことや、学生時代に何らかの理由で親友が自害したことが関係しているようだった。
■ある時、私は先生に「死ぬ前にたった一人でいいから、人を信用して死にたい。あなたはその一人になってくれるか。あなたは真面目か」と問われた。先生はいつか、自分の過去を私に語ることを約束した。
第2部 両親と私
■私は大学卒業後、実家に戻ったが、その後の進路は決まっていなかった。父母に促されるがままに、仕事の斡旋をお願いする手紙を先生に書いたが、返事は帰ってこなかった。
■父の容態が悪化したため、電報を打って兄を呼び寄せた。兄は先生について「人は自分の持っている才能を働かせなければいけない」と父と同じようなことを言った。父の死後も実家に戻るつもりはなく、とにかく世の中で仕事をしたいようだった。私は死にゆく父と個人主義的な兄の手前、先生に書いた手紙の返事を待ちわびていた。
■しかし届いたのは、先生の過去を洗いざらい告白した、先生の「遺書」だった。私は父が死の間際にあるにもかかわらず、母と父に手紙だけ置いて、東京行の汽車に飛び乗った。
第3部 先生と遺書
※以降の「私」は先生を指す
■私は20歳になる前に両親を亡くした。故郷の実家は資産家だったため、しきたりとして妻を娶り、家を相続する必要があった。私はそれを理解していたものの、叔父が従妹(=叔父の娘)との結婚を勧めてきた際には、さすがに幼馴染とは恋はできないと思って断った。
■しかし後から考えると、その結婚は、事業に失敗した叔父が父の財産を総取りするための策略だった。結果的に結婚は断ったものの、家の財産は叔父に使い込まれてしまった。私は不当に減った遺産を受け取るか、叔父を訴えるかの二択に迫られたが、無駄な時間は使いたくなかったので前者を選んだ。
■それでも普通の学生よりはお金に不自由していなかったので、下宿を出て、軍人の未亡人宅を間借りすることにした。人を信じなくなったが、愛をまだ信じていた私は、そこの一人娘であるお嬢さんに好意を寄せた。
■私はその3人の生活に「K」という同郷の幼馴染を引き入れることになる。Kは寺の息子だが医者の家に養子に出されており、大学でも医学を学ぶはずだった。しかしKは私と同じ学科に進んだため、実家からも養家からも勘当されてしまい、精神的に参っていたのだった。
■幼いころから成績は常にKの方が上だったが、禁欲的に自分を追い詰めるところや、女性慣れしていないところについては、私の方がよく事理を弁えていた。私がKを今の生活に引き入れたのは、未亡人宅で私自身の心身が以前より落ち着いたのと同じ効果をKに期待したためだった。
■その後、Kは精神衰弱から徐々に回復し、お嬢さんに好意を持ち始めると、逆に私は焦り、嫉妬し、劣等感に苛まれた。しかし、学問で繋がったKとの関係性の中で、人間らしい「恋愛」の話を持ち出すのは憚られた。私はKを呼び寄せたことを後悔した。
■ある日、Kは私にお嬢さんへの恋心を自白した。私は苦しく、恐ろしく、何も言えなかった。Kに先を越されてしまった。しかしKは完全に私を信用している。そこで私は「精神的に向上心のない者はばかだ」と、Kが以前私に言い放った言葉をそのまま返し、禁欲的な信条を持つ彼に恋を諦めさせようとした。私は卑怯であった。
■Kに先を越されまいとした私は、先に奥さんにお嬢さんとの結婚の許可を求めた。奥さんは条件もなく快諾したので拍子抜けだった。私はKに手をついて謝りたかったが、奥さんとお嬢さんの目もあったので、それは叶わなかった。それどころか、自分からKに事情を説明することすらしなかった。
■結局、Kは私とお嬢さんの結婚を奥さんから聞くことになったが、平静とした態度を変えなかった。それから数日後、Kは自殺した。私宛の手紙が残っていたが、私の裏切りについては書かれていなかった。正直なところ、私はほっとした。
■私はKに策略では勝っても、人間としては負けたのだった。私は叔父に裏切られて他人に愛想を尽かしたが、Kの件で自分に愛想を尽かし、何もできなくなってしまった。そして、明治天皇の崩御、そして乃木大将がその後を追ったことを知り、自分も「明治の精神」に殉死することとした。
学びのポイント
近代的自由と孤独
自由と独立と己とにみちた現代に生まれた我々は、その犠牲としてみんなこの寂しみを味わわなくてはならないでしょう。
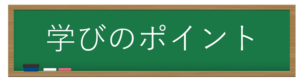
この「近代人の自由と孤独」は、本作品における最大のテーマと言われている。すなわち、仁・義・礼・誠などを貴び、恥ずべき言動をしないという日本的な武士道精神を貫くのであれば、「私」はKを裏切り、自殺に追い込むようなことはなかった。しかし、自分自身の自由意思を貫いてしまったからこそ、最後には親友を失い、孤独に苛まれることになってしまった。
漱石は別の場所でこんな言い方もしている。
現代はパーソナリティーの出来るだけ膨張する世なり。而して自由の世なり。(中略)
彼らは自由を主張し個人主義を主張し、パーソナリティーの独立と発展を主張したる結果、世の中の存外窮屈にて、滅多に身動きもならぬを発見せると同時に、この傾向をどこまでも拡大せねば、自己の意思の自由を害する。
つまり、自由・独立・個人主義を標榜した瞬間、それらを守るために、何かに依存したり従うことは徹底的に排除される。すると結果的に、人間は周囲との繋がりを絶たれ、孤独になる。漱石はそれを「存外窮屈」とか「身動きもならぬ」と言っている。
そして自由と個人主義が行き過ぎると、逆説的に、人は何かに従いたくなる傾向があり、例えばドイツの哲学者ニーチェは著書『善悪の彼岸』でこう言っている。

歴史を振り返ると、先導者より服従者の方が圧倒的に多数派だ。人は自由に耐えられず、自ら喜んで服従する性質を持っている。(中略)
この家畜的なヨーロッパ人にとっては、無条件に命令を下す者の出現が、どれほどまでに好ましいものであることか、そして耐えがたくなりつつある窮地からどれほどに解放してくれるものであることか。
ナポレオンの出現がきわめて大きな影響を及ぼしたことが、その最後で最大の証言となるのである。
ニーチェはこの時ナポレオンを先導者の例として挙げたが、歴史はその後も繰り返すことになる。
『善悪の彼岸』から下ること約150年、『こころ』から下ること約30年、ドイツの社会心理学者エーリッヒ・フロムは著書『自由からの逃走』で以下のようなことを述べ、自由から逃れたかった人々がナチスに傾倒したと結論付けている。
・人間は、自分の意思で「自由」を求めていると信じている。
・しかし、人間は自由になればなるほど、心の底では耐えがたい“孤独感”や“無力感”に苛まれる。
・そして孤立する恐怖から逃れるため、自由から逃避し、盲目的に何かに服従するようになる。
いかがだろうか。特に「人は自由になればなるほど孤独になる」という点は、漱石と全く同じ主張と言える。
本書『こころ』が書かれた1914年は、日本が開国後、急速な近代化により欧米列強と肩を並べ始める時期と符合している(1895年日清戦争勝利、1905年日露戦争引き分け、1914年第一次世界大戦参戦)。
急激な欧米化、すなわち自由・独立・個人主義の台頭により、日本人も何らかの孤独に苛まれていたのかもしれない。
精神的に向上心のない者はばかだ
(K→私)
たしかそのあくる晩のことだと思いますが、二人は宿へ着いて飯を食って、もう寝ようという少しまえになってから、急にむずかしい問題を論じ合いだしました。Kはきのう自分のほうから話しかけた日蓮の事について、私が取り合わなかったのを、快よく思っていなかったのです。精神的に向上心がない者はばかだと言って、なんだか私をさも軽薄もののようにやり込めるのです。
(私→K)
私はまず『精神的に向上心のない者はばかだ』と言い放ちました。これは二人で房州を旅行しているさい、Kが私に向かって使った言葉です。私は彼の使ったとおりを、彼と同じような口調で、再び彼に投げ返したのです。しかしけっして復讐ではありません。私は復讐以上に残酷な意味をもっていたということを自白します。私はその一言でKの前に横たわる恋の行手をふさごうとしたのです。
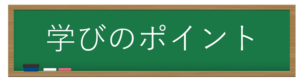
本作品で、最も有名な一節は何かと問われれば、恐らくこの「精神的に向上心のない者はばかだ」というセリフが挙がるだろう。
これはもともと、しっかりと議論と向き合わない「私」を見下して「K」が言い放った言葉だった。Kは寺の息子らしく、禁欲的で、生真面目で、強情で、誇り高い。向上心を持たない者を完全に見下していた。
しかし、そのKがあろうことかお嬢さんへの恋にうつつを抜かしてしまう。私は何とかしてその恋を止めなくてはいけない。そこで最も効果的であると私が選んだのが「精神的に向上心のない者はばかだ」と言い返すことだった。Kが最も大切にしている価値観を否定し、Kの存在自体を否定してしまう、悪魔のような仕打ちだったと言えるだろう。
私はそれを理解しており、この発言を後に後悔することになる。
父と先生の対比
私は心のうちで、父と先生とを比較してみた。両方とも世間から見れば、生きているか死んでいるかわからないほどおとなしい男であった。人に認められるという点からいえばどっちも零であった。
それでいて、この将棋を差したがる父は、たんなる娯楽の相手としても私には物足りなかった。かつて遊興のために往来をしたおぼえのない先生は、歓楽の交際から出る親しみ以上に、いつか私の頭に影響を与えていた。ただ頭というのはあまりに冷やかすぎるから、私は胸と言い直したい。肉の中に先生の力がくい込んでいると言っても、血の中に先生の命が流れていると言っても、その時の私には少しも誇張でないように思われた。(中略)
私はほとんど父のすべても知り尽していた。もし父を離れるとすれば、情合のうえに親子の心残りがあるだけであった。先生の多くはまだ私にわかっていなかった。話すと約束されたその人の過去もまだ聞く機会を得ずにいた。
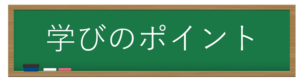
この「父」と「先生」の対比も、本書を貫く主要なテーマの一つとなっている。どちらも社会に何の貢献もしていないし、存在してもしなくても、社会に影響はない。
しかし、「父」は東京の大学に通う「私」から見ると、凡庸の代表である。田舎者、教養に欠ける、大学を出れば高給が得られると思っている、周り近所から見える体裁を気にするなどなど。父とは関係が近すぎて、私は父の全てを知っているものと思い込んでいる。
一方の「先生」はミステリアスである。多くを語らない、教養は深そう、何やら暗い過去を抱えている。二十歳前後の若者には、父親よりも優れている人が外にたくさんいることに気が付く瞬間がある。これは、誰しも経験することだろう。
しかし「私」はそこまでドライな人間ではない。父がやたらと大学卒業を「結構なこと」を言うのに対し、当初「私」は「そこまで大したことではない」と反発する。しかし「父」が自分の死期の近いことを悟ったうえで、自分が生きている間に息子が大学を卒業するのが(父にとって)結構なことと言っていることに気付くと、以下のような反省をする。
私は一言もなかった。謝る以上に恐縮してうつむいていた。父は平気なうちに自分の死を覚悟していたものとみえる。しかも私の卒業するまえに死ぬだろうと思い定めていたとみえる。
その卒業が父の心にどのくらい響くかも考えずにいた私はまったく愚か者であった。私は鞄の中から卒業証書を取り出して、それを大事そうに父と母に見せた。
「私」の心の動きを見事に描写した一節と言えるのではないだろうか。
人事部長のつぶやき
恋には清新さが必要
しじゅう接触して親しくなりすぎた男女のあいだには、恋に必要な刺激の起こる清新な感じが失われてしまうように考えています。
香をかぎうるのは、香をたきだした瞬間にかぎるごとく、酒を味わうのは、酒を飲みはじめた刹那にあるごとく、恋の衝動にもこういうきわどい一点が、時間のうえに存在しているとしか思われないのです。
一度平気でそこを通り抜けたら、慣れれば慣れるほど、親しみが増すだけで、恋の神経はだんだん麻痺してくるだけです。私はどう考え直しても、この従妹を妻にする気にはなれませんでした。
これは、叔父から従妹(=叔父の娘)との結婚を迫られた先生が心情を吐露する箇所。
恋には「香りを最初に嗅ぐ瞬間」や「酒を最初に飲む瞬間」に似た刺激が必要であることを述べている。なんとも比喩が美しく、素晴らしい。

名文家、夏目漱石の本領発揮!という一節です!
多様性の大切さ
Kははじめ女からも、私同様の知識と学問を要求していたらしいのです。そうしてそれが見つからないと、すぐ軽蔑の念を生じたものと思われます。今までの彼は、性によって立場を変えることを知らずに、同じ視線ですべての男女を一様に観察していたのです。
私は彼に、もし我ら二人だけが男同志で永久に話を交換しているならば、二人はただ直線的に先へ延びて行くにすぎないだろうと言いました。彼はもっともだと答えました。
明治時代はまだまだ男尊女卑的な空気が強かったが、この「私」の言い分は、多様性の重要性を的確に表している。
男女は社会的には平等だが、生物学的には明確に異なっている。例えば、一般的に(平均的に)男性の方が背は高く、論理的思考や空間把握能力に優れているとされる。そして女性の方が言語能力やコミュニケーション能力は高いとされている。
だから、同じような特徴を持つ同性だけで議論しても、広がりが無く「ただ直線的に先へ伸びて行くに過ぎない」ということになる。
これと全く同じようなことを、元IMF専務理事のクリスティーヌ・ラガルド氏が、IMFのブログでこう綴っている。

この意味で、改革の重要な要素のひとつとして、金融業界で幹部として活躍する女性の数を増やすことが挙げられると思います。これにはふたつの理由があります。
第一に、多様性が豊かであるほど、例外なく思考が研ぎ澄まされ、集団思考のリスクを減らします。第二に、多様性が高まると慎重さも増し、危機を引き起こしたような無謀な決定が行われにくくなります。銀行の取締役や金融監督機関の幹部に占める女性の割合が高ければ高いほど安定性が増すことが、私たち自身が行った研究で証明されています。
繰り返し言ってきたことですが、もしリーマン・ブラザーズがリーマン・シスターズであったなら、今日の世界は大きく違ったものになっていたかもしれません。
原文 https://blogs.imf.org/2018/09/05/ten-years-after-lehman-lessons-learned-and-challenges-ahead/

リーマン・ブラザーズは男性だけで「直線的に」突っ走ってしまった、ということですね
.png)

