「方丈記」鴨長明
基本情報
初版 1212年
出版社 角川ソフィア文庫、光文社古典新訳文庫等
難易度 ★★☆☆☆
オススメ度★★★★☆
ページ数 189ページ
所要時間 2時間00分
どんな本?
枕草子、徒然草と並ぶ日本三大随筆の一つ。「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」という書き出しで有名。この世の無常と生きづらさ、そして世俗を離れた自身の生活を生き生きした文体で著すが、最後には「悟りきれない」自分を反省する。
面白いことに、古代ローマ皇帝アントニヌスも著書「自省録」の中で「すべての存在は絶え間なく流れる河のようであって、その活動は間断なく変わり、その形も千変万化し、常なるものはほとんどない」と鴨長明と全く同じことを言っている。両書を読み比べて「諸行無常」の思想を学ぶのもおすすめ。
著者が伝えたいこと
世の中に確実なものなど一つもなく、都での生活・社会的地位・財産・人間関係等にあくせくと執着するのは愚かなことである。
だから私は世俗を離れ、狭い庵で質素かつ自由気ままに暮らしたのだが、それもそのような生活に執着していただけであった。人生とは何とも悟りきれず、難しいものだ。

著者
鴨長明 1155年-1216年

京都の下鴨神社の神官であった鴨長継(かものながつぐ)の子。当時においては知識階級であり資産家。若いころに神職界において後ろ盾となるべき父を亡くしたため、琵琶と和歌の道に進む。
1201年、後鳥羽上皇の命で設立された和歌所で選歌委員として働き、藤原定家との歌合せでは四戦無敗だった。「源家長日記」には「まかり出づることもなく、夜昼、奉公おこたらず」と、長明が熱心に勤務した様子が記されている。
1204年、下鴨神社の系列である河合神社の神官への就任を望み、後鳥羽天皇の内諾を得るが、対立する親族の反対で実現せず、失意のうちに出家する。数年後、鎌倉に出向き、将軍源実朝の和歌の師範となるべく面会したが、それも叶わなかった。
本書「方丈記」は、鴨長明が晩年に居住した方丈庵(一丈四方、すなわち約3.3メートル四方の小さな家)で書かれており、書名の由来にもなっている。

こんな人にオススメ
日常生活に少し疲れた人、世の中は生きづらいと思っているのは自分だけではないことを確認したい人
書評
古典の授業で習うくらいだから、さぞかし高尚な人が高尚なことを書いているのだろうと思いきや、決してそんなことはなく、世俗から離れたくても離れられない鴨長明の人間臭いドラマが展開されている。
「執着から逃れるために、山で隠遁生活をしてみたが、結局私はその隠遁生活に執着していたのだ」という、超基本的なパラドクス構造を持つことが、古典として現在まで残っている所以だろう。
本文自体は短いので、解説を飛ばせば1時間弱で読了できる。自分の人生について考える余裕のある一人旅のお供にオススメ。
要約・あらすじ
■流れている河の流れが途絶えることなく、それでいてそこを流れる水は、もとの水ではないように、世の中のすべての現象は常に変化し、生まれは滅び、永久不変なものはない。
■最近、京の都では「大火」「竜巻」「飢饉」「疫病」「大地震」といった災厄が続いたが、まさに無常の世の中である。豪邸を構えたところで、全てを失うことになるのだ。人間は一体この世において、何に執着すると言うのだろう。
■時の権力者は成り上がりものの平家で、平清盛は都としての歴史ある京都を捨てて、福原(現神戸市)に遷都した。京の街は廃れていくし、貴族らしい雅な文化も失われていく。こちらも無常である。
■そもそも、人生とは苦労の連続だ。人それぞれ、置かれた環境や身分・立場に応じて苦労の種が次々に生まれてくる。地位や財産は、あればあったで心配の種は尽きないし、貧しければ貧しいで、嘆きの種は尽きない。とにかくこの世は住みにくい。
■私(=鴨長明)は相続争いに敗れ、その後、思い立って50歳の春に出家した。しかし、大原で5年間修業したものの、何の悟りも得ることが出来なかったので、京の外れに方丈庵を建てて住み、現世への執着を絶つ生活を実践することにした。
■方丈での生活は自然に囲まれ、自由気ままである。歌を詠み、琵琶を弾き、近所に住む10歳の少年と野山を散歩する。読経に身が入らなければ途中でやめればよい。他に誰もいないから、気を遣うこともない。朝は宇治川を眺め、夜は月に想う。無常の世の中において、この方丈庵だけは変わらない。
■自分一人が生きていくだけであれば、衣食住は質素で十分だ。人間は利己的で付き合いも面倒だから、友達も使用人も持たない。私心は無く、もはや自分の命も惜しくない。都の人間の、なんとあくせく生きていることよ。この心の安らぎは何物にも代えがたい。
■しかし考えてみると、私は「執着心を捨てよ」という仏の教えに反して、日々の生活に追われる都の人々を見下し、方丈での質素な生活に執着していた。もはや何を言っても言い訳になる。無心にならなくてはいけない。そこで私はただ「南無阿弥陀仏」と、二度三度唱えたのだった。
学びのポイント
諸行無常という考え方
行く河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。
(流れ過ぎていく河の流れは途絶えることがなく、それでいてそこを流れる水は、もとの水ではない)
淀みに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし。世の中にある、人と栖と、またかくのごとし。
(よどみに浮かんでいる水の泡は、一方では消えてなくなり、一方ではできたりして、長い間そのままの状態でとどまっている例はない)
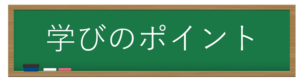
方丈記と言えば、まずこの出だしが超有名。この箇所は、「生きるとは何か」という問いに対する釈迦の最終結論である「三法印」の中の「①諸行無常」について語っている。
(関心のある方は『スッタニパータ(ブッダのことば)』をご参照ください)
【三法印】
①諸行無常:世の中のすべての現象は常に変化し生滅して、永久不変なものはない
②諸法無我: 世の中のすべての現象には主体などない
③涅槃寂静:煩悩を全て消し去ると、穏やかな世界が待っている
平たく言えば、人間関係にしても、財産にしても、自分自身にしても、あらゆるものは常に変化していて、永遠に存在するものなどないのだから、執着するだけ無駄、ということになる。
この冒頭分はどこかで見たことがあると思っていたところ、ローマ皇帝マルクス・アウレリウス。アントニヌスが自著『自省録』で、まったく同じ趣旨のことを述べていた。

すべての存在は絶え間なく流れる河のようであって、その活動は間断なく変わり、その形も千変万化し、常なるものはほとんどない。
我々のすぐそばには、過去の無限と未来の深淵とが口をあけており、その中にすべてのものが消え去って行く。
このようなものの中にあって、得意になったり、気を散らしたり、または長い間ひどく苦しめられている者のように苦情を言ったりする人間は、どうして愚か者でないであろう。
鴨長明が『自省録』を読んでいたとは思えないので、偶然の一致ではあるが、2000年前のローマと、800年前の日本で、同じようなことが語られていたかと思うと、なかなか感慨深い。
なお、方丈記には以下のような記述もあるが、これはフランスの画家ポール・ゴーギャンの「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」を彷彿とさせる。
私には分からない。生まれ死んでゆく人は、どこからやってきて、どこに去っていくかを。また、生きている間の仮住まいを、誰のために心を悩まして建て、何のために目を嬉しく思わせようとするのかを。

本作を手掛ける直前のゴーギャンは、愛娘アリーヌを亡くしたほか、借金を抱えた上に健康状態も悪化するなど、失意のどん底にあった。本作を描き上げた後、(未遂に終わるが)自殺を決意しており、この絵を自身の画業の集大成と考え、様々な意味を持たせたと言われている。
自分とは何者なのか、この世はどれほど儚いものか、人間は苦しい状況に置かれると、こういったテーマを考えるのであろう。それには古今も東西もない。
人は災害を忘れてしまう
地震直後のしばらくは、誰もかれも、天災に対していかに人間が無力であるかを語り合い、少しは欲望や邪念といった心の濁りも薄らいだように見えた。
だが、月日が経ち、何年か過ぎてしまうと、震災から得た無常の体験などすっかり忘れ果て、話題に取り上げる人さえいなくなった。
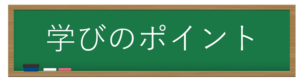
これは現代にもそのまま当てはまる、普遍的な警告と言えるだろう。三陸沖では歴史的に何度もマグニチュード8以上の地震が起き、津波が発生していても、その教訓を生かしきれず、2011年の東日本大震災では18,000人以上の方が亡くなった。
1923年に関東大震災を経験した物理学者の寺田寅彦は、著書「津波と人間」でこう書き残している。

しかしそれ(=災害を頻繁に発生させること)が出来ない相談であるとすれば、残る唯一の方法は、人間がもう少し過去の記録を忘れないように努力するより外はないであろう
2020年に始まった新型コロナウィルスによる疫病も、いずれ過去のものとして人々の記憶から薄れていくのかもしれない。
とかくこの世は住みにくい
財産があればあったで、心配の種は尽きないし、貧しければ貧しいで、嘆きの種が尽きない。他人に頼りすぎると自主性がなくなり、他人をせわしすぎると自由がなくなる。世間の常識や慣習に合わせすぎると窮屈だし、全く合わせないと奇人変人扱いされる。
では一体、どんな場所に住み、どんな仕事を選んだら、心安らかに過ごすことが出来るのだろうか?いや、この無常の世で、そんな場所や仕事を見つけることは到底無理だろう。
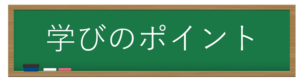
長明は「無常観」とともに、この世の中の「生きづらさ」を強調している。長明が資産家一族の出身であることは割り引いて考える必要があるが、世の中が「生きづらい」と感じるのは自分だけではないと勇気付けられる面もあるのではないだろうか。
住む環境や仕事といった外部の要因は、決して心の安らぎを与えてくれない。とすれば、自分自身の中にそれを求めるしかない、ということを言いたいのだろう。
なお「世の中の生きづらさ」を表現した名文と言えば、真っ先に夏目漱石『草枕』の冒頭が思い浮かぶ。

智に働けば角が立つ、情に棹させば流される、意地を通せば窮屈だ。
とかくに、人の世は住みにくい。
『草枕』
理屈や論理に頼りすぎるとぎくしゃくする、感情が過ぎると主体性が無くなる、自分を押し通そうとすると世間は狭くなる。本当にこの世の中は生きづらい。といった内容を、見事な五七調で言い表している。文章の構成が方丈記にそっくりなので、漱石は意識をしたのかもしれない(注:根拠はありません)。
最後の最後で大どんでん返し
仏の教えは「執着心を捨てよ」というものだ。しかし私はそれに反して、日々の生活に追われる都の人々を見下し、方丈での質素な生活に執着していた。
もはや何を言っても言い訳になる。無心にならなくてはいけない。そこで私はただ「南無阿弥陀仏」と、二度三度唱えたのだった。
第35段・36段の趣旨を要約
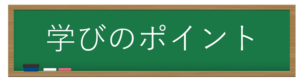
方丈記は第1段から第36段まであるが、第34段までは「世の中は無常であること」「都で住まいや出世に執着するのは愚かであること」「自分は世俗を離れて風雅な暮らしをしていること」を滔々と説く。
しかし、最後の2段では一転、そんな自分も方丈での生活に執着していたのだと自省する。本来であればその自省の内容が語られるべきであるが、何を言っても言い訳になるというわけで、最後の最後は「念仏を唱えて」終わってしまう。
この終わり方には様々な評価があり、あまりに中途半端であると批判する解釈もあれば、悟りきれなかった自分を素直に反省する長明の人柄が出ているのだと評価する解釈もある。
どのような解釈も可能だが、方丈庵での生活を経験した長明が、最後には「人の生き方に模範などない。ただし、人の幸せは住まいや地位等にあるのではなく、それぞれの心の中にあるのだ」ということが言いたかったのではないだろうか。
人事部長のつぶやき
悟りきれない生身の人間、鴨長明
住みわびぬ いざさは越えん 死出の山 さてだに親の 跡を踏むべく『鴨長明集』
生きるのが厭になった。この世で父の跡目を継げないなら、せめて死ぬことで亡き父の跡を継ごう。
鴨長明集
鴨長明は名門の家に生まれたにもかかわらず、相続争いに敗れ、神職を得ることもできず、失意のうちに出家するという人生を歩んでいる。本書で「諸行無常」を説いたのも、自身の人生が色濃く反映された結果であると言えるだろう。
しかし、出家はしたものの、5年経っても何の悟りも得られなかっただけでなく、官位を得ようと鎌倉まで源実朝に会いに行ったりもしている。
その後、本書が書かれた「方丈」に引っ越すわけだが、場所は京都の外れではあるものの、山奥というわけではなく、何かと生活しやすい場所を選んでいる。現代で言えば、田舎でスローライフと言いつつ、常にSNSをチェックするようなもので、なんとも中途半端な出家生活であった。

悟ろうとしても悟りきれない、人間臭さが感じられますね
断捨離の元祖、鴨長明
新たに作ったその家構えは、世間一般のものとはまるで違う。広さはやっと一丈四方(約3 メートル四方。今の四畳半)で、高さは七尺(約2メートル)にも満たない。
長明は「方丈庵」の中の様子を克明に記載しており、それを図示すると以下のようになる。
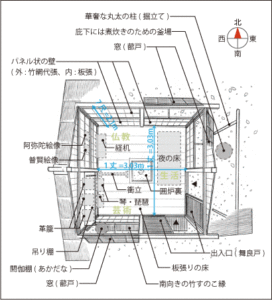
現代風に言えばミニマリストであり、断捨離の走りと言えるだろう。それでも、仏像や経典はいいとして、歌書・音楽書・琴・琵琶などがあり、風流な生活は捨てきれなかったようだ。

老後、静かに暮らすには十分なのかもしれませんね
いいとこのお坊ちゃん、鴨長明
人の心もまるで変わってしまった。雅な公家ふうを捨てて、実利優先の武家ふうに染まり、馬や鞍ばかりを重んずる。(中略)
路上を見れば、牛車に乗るはずの公卿が武士のように馬に乗っている。衣冠や布衣をつけるはずの公家の身分なのに、多くが武家ふうに直垂を着ている。貴族の雅な風俗は急速に変わって、まるで田舎武士と同じになってしまった。
名門下鴨神社の神官一族に生まれた鴨長明だったが、時の権力者は、当時の貴族階級から見れば「成り上がりもの」の平家一族だった。
鴨長明にはそれが許せなかったのだろう。京都が貴族の街から武士の街に変わっていく様を嘆いている。

鴨長明が生きたのは、1156年保元の乱、1159年平治の乱で、平清盛が政治の実権を握った時代と重なります
.png)

